「健康経営にゴールは設けない。常に進化させていくものだから」
株式会社フジクラ人事部・健康経営推進室 副室長 浅野健一郎氏
昨年から「健康経営銘柄」の発表が始まり、今年は「健康経営優良法人」が発表されるなど、年々、健康経営に注目が集まっています。
しかし、実際どれだけの企業が社員を健康にできて、収益改善に貢献できているのでしょうか!?
この業界に20年にわたって関わり続け、多くの企業と情報交換している我々でも、“健康経営が実って収益が改善した”との話しはほとんど聞こえてきません。まだ始まったばかり、というのが実態かもしれません。
そのような現状のなか、すでに何年も健康経営に取り組み、成果を出し始めている企業も存在します。
mHealth Watchでは、成果を出し始めている企業がどのような取り組みをしているのか、モバイルヘルスをどう活用すると貢献するのかなど、具体的なアプローチにスポットを当てて特集を組んでいきます。
今回は第1弾として、株式会社フジクラで健康経営の企画段階からリーダーとして携わってきた浅野健一郎氏にお話しを伺いました。(取材日:3月7日/インタビュアー:渡辺 武友/撮影:小松 智幸)
組織内で小さな変化が常に起きることで、全体としても良い方向にシフトする
 Q:健康経営の取り組みは、構想4年、実行3年で、それなりの結果に結びついていると伺いました。
Q:健康経営の取り組みは、構想4年、実行3年で、それなりの結果に結びついていると伺いました。
詳細は4月20日のヘルスケアITのセミナーでお話しいただくとして、今日はどのようなことが結果に結びついたのかを伺いたいと思います。
まずは、3年で結果が出ると正直思われていたのですか?
A:いえ、まったく思っていなかったですね。
もともと私たちは結果がすぐ出るものではないと想定していました。健康経営を経営施策として遂行していくに当たり、どのように評価していくかを議論していたのです。
もう少し詳しく話すと、ファーストステップとして、社員の健康状態が良くなっていき、最終的に経営的に事業成績が良くなっていく。その過程で誰かがなにか行動を変えるだろうと。その行動を捉えることができれば、どう変わったかのKPIになると考えました。
そのようなことを考えた時、そもそも3年くらいでは健康度が上がるとは思っていなかったのです。
Q:なぜ3年では変わらないと考えたのですか?
A:行動してくれる人とそうでない人に分かれるためです。“健康オタク”な人たちは、なにか提供すればすぐに行動してくれますが、絶対にやりたがらない人たちもいます。またその中間くらいの人たちもいます。
最初になにかしらのデータが出てくるのはオタクでもなく、そういうことが嫌いでもない、非常に限られた層からしか動いていかないと考えたのです。
Q:行動する人しない人は、どのような比率なのですか?
A:大まかに分けると、オタク層が2割、その次の層が3割、4割がやりたくない層で、残りの1割が絶対やりたくない層です。
Q:結果的には、やりたくないと思っていた人たちも動いたということでしょうか?
A:そうです! これには私たちも驚きました。まったくの想定外でしたね。
このような取組みを会社が始めると、やりたいと思う人だけが始めて、やりたくない人は絶対にやらないため、健康格差が広がるだろうと思っていたのですが、実際には、いやだと思っていた人たちの健康度が良くなっていたのです。
Q:それはなぜですか?
A:行動をしている人たちに、引きずられているようです。
Q:でも行動はしていないのではないですか?
 A:私たちが観測している行動には出てこないのですが、どうやら集団内の相対値関係では動いていないとしても、人は絶対値的な立ち位置で動いているということだと思います。
A:私たちが観測している行動には出てこないのですが、どうやら集団内の相対値関係では動いていないとしても、人は絶対値的な立ち位置で動いているということだと思います。
集団全体が健康行動寄りになっていくと、やりたくない人たちも、この分布を守ったままシフトしているのです。
Q:それは提供された健康施策には参加しない人でも、そういう話題が回りに常にあるため、なんとなく耳にすることで、自分なりに健康行動をしてしまっている。ということでしょうか?
A:そうなんです。数値を取っている歩数などでは変化は見えてこないのですが、体重が減っていっているので、おそらく食事の時など、なんとなく得た情報から、できることを取り入れているのではないかと思います。歩数では見えない運動をしているのかもしれないのですが。
Q:体重が落ちるということは食事でなにかしら気を使っていそうですね!?
A:そうだと思います。なんとなく情報が入ることで、今までの常識と思っていた基準のラインが動いているのです。
例えば、飲酒が好きで肝機能が悪くなりつつある人たちに取り組んでほしいと思い、「節酒プログラム」を提供しています。セミナー形式のもので、参加者は1回に10人程度です。
本社には1,000人ほど従業員がいまして、このプログラムの対象者は数百人にもなります。この辺は飲み屋も近くにたくさんありますから(笑)。
1回のプログラム参加者が10人程度だと、複数回やっても全体の1/10くらいにしかアプローチできていないことになります。しかし、この事業所全体の肝機能に関する数値が良くなっているのです!
これは口コミ効果によるものだと思われます。いつもどおり何人かで飲み屋に行った時、そのなかにプログラム参加者がいると、そのときに教わったことを話題にするわけです。そうすると、プログラムに興味を示さなかった人でも、仲間から教わったことなので自然と取り入れてしまっているようなのです。
Q:理想的な展開ですね!
A:そうなんです。目に見えないところで行なわれることで、劇的に変化するとは想定していなかったですから。
Q:このプログラムだから効果があった、というレベルではないですね。
A:もちろん、このプログラムが効いたという体験者がいて、それを自慢するというプロセスは必要になると思っています。それが口コミとして広がったところが全体の効果につながっているわけです。
今回のことで、会社というある程度閉じられた社会空間のなかで、ある意味で家族より長く過ごしている人たちが、そのなかでなにか変わっていくことに、全体が引きずられていくということが初めて理解できました。
Q:フジクラさんの健康経営では、通年をとおしたウォーキング系のものがベースにあって、先程の「節酒プログラム」のようなものが、色々な課題ごとに提供されていますね。それこそ月に何本もイベントが同時に走っているような状態だと思います。
そのように、常に色々な角度から健康に関する情報が提供されることで、感度の高い人が実践し、身近な人に伝えているわけですね。
A:そうだと思います。教育ではなくて、自然と情報が入ってくる。そこが重要だと思うのです。
例えば、階段のところに消費カロリーが貼ってあります。1フロア登ると1.6kcal、降りると1.3kcalと書いてあります。一方、自動販売機にも飲料の摂取カロリーを貼ってあるわけです。このような情報を何気なく見ているだけでも、「この飲料を1本飲むと161kcalと書いてあるけど、階段を1フロア登ると1.6kcalしか減らないって書いてあったな。ということは、これ飲むと100階分上がらないとダメなのか」と自分で考え出すのです。
それがワンタイムの研修として、このようなジュースは何kcalと教えたとしても、すぐ忘れてしまいます。その人の行動のなかで“自分で気づく”というところに持っていくことが重要になります。すべては自分で気づくことが大切なのです。
 健康行動が嫌いだと思っている方々も、太りたいと思っているわけでもないし、不健康になりたいと思っているわけでもない。しかし、今の生活習慣を変えたいとは思っていない、好きなことをやりたいわけです。プライオリティが人によって違うということです。
健康行動が嫌いだと思っている方々も、太りたいと思っているわけでもないし、不健康になりたいと思っているわけでもない。しかし、今の生活習慣を変えたいとは思っていない、好きなことをやりたいわけです。プライオリティが人によって違うということです。
もうひとつは情報教育がされていないことです。情報がきちんと身に付き、その知識の元に理解できたとしたら行動は変わっていきます。しかし、これを強制的な教育としてやってはダメなのです。自分なりの解釈でわかっていかないと本質的な理解にはなりません。無理をすれば、さらなる拒否反応になってしまいます。
ですので、先程の階段の消費カロリーのように、自然と目につくところに情報を置くこと、そして色々な体験型の健康イベントを提供することです。健康セミナーやオンラインプログラムなどは、興味を持った人しか参加しませんが、それで良いのです。参加者がイベントを楽しんでいたり、成果を出してくれれば、イベント自体に興味を示さなくても、その人の話題が耳に入るだけでリテラシーは変わってきます。
このような相乗効果で集団全体が良くなっていったということです。
“病気の状態をなくす”のではなく、“活き活きと働ける”環境を作る
Q:我々も、新たに健康経営に取り組みたい企業と話す機会がありますが、なにかひとつの施策で解決させようとする傾向が強いと思います。これは違いますよね!?
A:あり得ないでしょうね。基本的な健康行動は誰でもわかっています。例えば、たくさん歩けばいい、食べ物を制限すればいいなど。しかし、それができるなら苦労はないわけです(笑)。
なぜ集団をひとつとして考え、なにか特定の施策だけをやりたがるかというと、会社という集団の健康とは“病気じゃない状態”と思っていることが多いようです。こう考えてしまうと、“病気の状態をなくそう”とのアプローチになってしまいます。
私たちは“活き活きと働く”ことができるのが健康な状態と考えています。そう捉えるとアプローチも変わってきます。例えば、肥満の人はなりたくてなっているのではないのです。昔は恰幅が良いとか、貫禄をつけるというので太ることを肯定していたかもしれないですが、今は肥満が体に良くないこともわかっています。同じくタバコを吸う人が、どれだけ自分に対してリスクか知らないで吸っている人はいないわけです。
ではなぜタバコを吸うのか? なぜ肥満になるような食べ方をする、もしくは運動をしないのか? そこが問題なのです。それは、その人の置かれている環境がそういうことを阻害しているからです。例えば、タバコの例がすごくわかりやすいです。一度禁煙した人もストレスが一気にかかる仕事、もしくはそういった状況に置かれると、ストレス発散のためにまたタバコを吸ってしまうことがあります。
その人が抱えている生活環境でのストレスの原因を排除しないで、体に悪いからとたばこだけ矯正させると、その人はバランスを取ることができなくなってしまいます。下手したら、たばこをやめることで、さらにストレスが追加され、メンタルを病んでしまうかもしれません。
もうひとつの考え方として、法律的に喫煙にしても食べることにしても認められているわけです。本来選択の自由があることを強制するのは難しいのです。
私たちのポリシーは、禁煙したい、減量したいと思った人がすぐに行動しやすい環境を作っておくことです。その人が気持ちに余裕ができた時に、その環境が身近にある。それを実践した人が身近にいる。費用がほとんどかからずできる。このように、その人にとっての行動の障害をどんどん取っていくわけです。
いくら良いことであっても、その人が余裕のない時はやらないし、やったとしても長期的効果には繋がりにくいものです。
多くの企業は医療費の削減などを掲げるわけですが、アプローチまで医療の視点が多過ぎるのではないでしょうか!?
今病気ではない人はそういうことでは動かないですし、興味もない。今、逼迫したなにかが起こっているわけでもないのです。生活習慣病がまさにそうじゃないですか。データとして病気と言われても、痛みを感じなければ病気の実感は伴わないわけですから。
Q:このままだと病気になると“脅す”だけではなく、もっとその人にとって魅力的なものを用意してあげて、ただ伝えるだけでなく、うまく口コミ的に持っていかないとその人たちは変わりようがないということですよね。
A:そのベースとして、いかにそういう人たちに余裕を作ってあげるかですね。
徹夜や残業をガンガンさせておいて、カロリーの高いものは食べてはいけません! それは無理な話です(笑)。
その人がどのような環境で、なぜそれを選択しているのか、もちろん家庭の問題もあるかもしれないですが。
Q:環境作りは部署単位でやっているのですか?
A:健康経営としてきちんとした労働環境を守るということはあります。まずは環境改善を会社全体でやり、そして部署は部署で問題があるのでそこでも改善していきます。実際は会社全体だけでなく、部署の問題とセットで考えます。
人間は環境から影響を受けることが多いのです。当初は個人へのアプローチが優先と思っていましたが、環境の方が大きいと思うようになりました。
Q:ストレスがかかっている人に対して、例えばどのように環境を変えたのでしょうか?
A:例えば、私たちは多くのデータを取っているので、ストレス度合いと長時間残業の関係で見ていくことができます。課題に対して、全体の集団で分析をかけたときに一番の要因として残業が上げられますが、なかには残業をたくさんやっているのにストレスが高くない人もいます。
皆さんもおそらくそうだと思うのですが、自分が目的を持って、自己実現でも組織の実現でもいいのですが共有して頑張っているときは全然辛くないのです。いくら残業しようが関係ないのです。しかし、強制的に残業させられて、これが本当に必要かもわからないのにやらせるとストレスになります。
この場合は抑制しなければいけないのですが、自分の目標に向かってやりたくて自己実現を含めてやっている残業を阻害したら、本人のためにも会社のためにもならないわけです。もちろん、いくらでも残業していいということではなく、心身の健康を確保できる節度ある残業の範囲ですが、ここで言いたいのは一律じゃないということです。どのような環境にすると、その人が活き活きとするのかを考えないとならないのです。
特にストレスになると家庭の問題が多いので、会社がなかなかアプローチできないところがあります。私たちが思っていることとしては、家庭だけの問題、あるいは仕事だけの問題でメンタル疾患になる人はほとんどいないのです。どこかに自分の居場所があれば、大抵は耐えられるものです。仕事がすごくきつくても、家庭がものすごく温かい場合、多くの人は病気になることはないんです。もちろん逆も言えます。
しかし、両方にストレスを感じると耐えられなくなるのです。家庭の問題に会社はアプローチできないですが、会 社側に問題があるならアプローチできるわけです。そこを取るだけで随分変わるのです。
社側に問題があるならアプローチできるわけです。そこを取るだけで随分変わるのです。
データ分析をかけてみると、残業と一致していないストレスが高い人たちや組織があるなど、良い方も悪い方も見えてきます。良い方はそれをひとつのモデルとしてどんどん広げていこうとなります。残業もいっぱいやっているけれど皆ストレス度合いは良く、生産性も高いのであれば、そこにひとつの解があるわけです。
Q:ストレスのチェックは以前から年1~2回問診を行なっていると伺いました。それで判断しているのですか?
A:ストレスを定量的に見るのは難しく、アンケート形式だと当然ながら偽装解答しようと思えばできてしまうので、それが本当の値かどうかもわからないですよね。しかし、それしかないので使うしかないのです。ただそういうデータだと認識して見ることが大切です。
私たちは、皆が活き活きと働けているようにしたいのです。活き活きと働けていない状態がストレスに現われます。ですので、会社として色々と施策を行なった時にストレスが大きくなっていれば、そのやり方に問題があるわけです。
ストレス以外の行動にも変化は見えてきます。今まで1日平均的に8,000歩を歩いていた人が住環境や職環境が変わっていないにも関わらず、ほとんど歩かなくなったのであればなにかあるわけです。
データ以外のことも重要です。例えば職場のなかでもわかります。今まで活発にコミュニケーションをとって、すごく人懐っこい人が突然喋らなくなったらその職場の人たちは気づきます。顔色や声のトーンだって気づきます。声を聞いた時に人同士だったら変化を感じ取ることができるのです。
部内などの小集団がそのような機能を発揮できる集団だとしたら、メンタルリスクはどんどんなくなっていきます。
しかし、自分のこと以外は余裕のない状態だと、他の人のことを見ていることができない。雑談や会話もなくなる。そうなると集団として人と人との見守り機能を発揮できなくなってしまいます。
そういう集団に何をするかというと、コミュニケーションをアップさせます。そもそも仕事量がすご過ぎてコミュニケーションどころではない場合もあるので、そこから調整していくこともあります。
私は多くの企業がやっているのは、データを統計的に見ているだけだと思うのです。それだけではなく、データを解釈してなにが起こっているのかをモデリングし、それで初めて分析と言えるのだと思います。そのような分析ができるから解決策が出てくるわけです。
なんとなくエクセルで統計を取りました。その程度でデータだけを見ていくと背景情報がわからない。こうなると逆のことをしてしまいやすいのです。
Q:数値だけ見て、追い詰めてしまうわけですね。
A:そういうことがないように、どうやっていくかというのが健康経営のなかでは重要になると思っています。
健康経営によって生産性を上げるとはなにか?
Q:健康経営に取り組むとき、生産性を上げることを目的にしますが、どうやって生産性と健康行動を紐付けるのが良いのでしょうか?
A:皆さんが求める生産性とは、おそらく定量的な数字が欲しいのでしょう。
工場でのものづくり労働であれば生産個数がどれくらい上がったかを見ればいいのですが、知的労働においては、アウトプットを定量的に測れるものではない。という前提に立たないと生産性は理解できないです。
ではどうするか? 私たちは割り切りだと思っています。その人が自分の生産性が上がっていると思うかどうか、しかないのだと思っています。
自分の生産性が上がってきているか落ちてきているかは自分が一番わかっているわけです。思考のなかなんて他人はわからないものです。その人が自分はこうやるとパフォーマンスを上げられる。こうやると自分の体調維持ができて、それは仕事としても良い方向に向かうなと感じることが重要になるのです。「感じている=その人の生産性が上がってきている」だと思います。
そのために定期的なアンケートなどから見ていきます。瞬間はバラつくので、絶対値なんてどうでもいいのです。人と人を比べても意味はありません。回答の傾向からトレンドはわかってくるのです。そして、その人を縦断的に見た時に、この人が良い方向に向かっているのか、悪い方向に向かっているのか、それがどのくらいなのかがわかるようになるのです。
Q:それをまた部署とかの単位の切り口で見ていくのですか?
A:色々な単位の切り口で見ていきます。個人もそうですし、小さなチームだったり、部や事業部だとか。部によって見方は変わるわけです。売り上げで測れるところもあればそうではないところもあります。
Q:それぞれ個を見ていったときに個が上がっていって、そこに対してなにかしらが経営に反映されていれば結果が出ているという判断ですか?
A:そうです。もちろん因果関係の証明はできないですし、寄与度も測れません。
これはもう限界がありますので。しかし、なにも指標を取れない状態からは天と地の差になります。
Q:それをまとめて定量的に数値で全部一緒にしようとするから、おかしな話になるわけですね。
A:そんなことはあり得ないでしょうね。でも、皆さんなかなかわかってくれないようです。なにかミラクルなツールがあるのではないかとよく聞かれます(苦笑)。
Q:ビジネスと同じように考えてしまうのではないでしょうか。短期で結果を出せと。それで短期で痩せさせることに目がいきがちですが、その場限りでプログラムが終わると元に戻ってしまう。これも経験しないとわからないようです。
 A:日本がここまで伸びたのは教育をしっかりしていたからですよね。教育をしっかりと受けたからボトムラインの人たちも応用力が付いた。これは製造、生産という意味での教育は成功したわけです。
A:日本がここまで伸びたのは教育をしっかりしていたからですよね。教育をしっかりと受けたからボトムラインの人たちも応用力が付いた。これは製造、生産という意味での教育は成功したわけです。
しかし、健康維持であったり、人間としての生きていく知恵という教育が抜けていたから、これだけ病気の人をたくさん作って、それが社会問題になってきているわけです。
そうやって見ていくと、結果が出るのには膨大な時間がかかります。しかし、今まで話したような集団単位である程度やると、今の状態が非常に悪い状態なので結構早く効果は出てきます。それだけベースが悪い状況なのだということです。これは弊社だけのことではなく、他も基本的には同じ、と言えます。
個別性が大切だが、パターンは絞られる
Q:健康経営の構想段階からお話しを伺っていまして、当時浅野さんから「これから色々なデータを取っていく。そのデータからこういうことしたら? とは伝えられるが、それだけでは人は絶対動くわけがないので、その人の趣味嗜好も合わせて、その人に合ったものを提示していくことをしたい」と聞きました。今はどのような段階ですか?
A:よく覚えていらっしゃいますね!
趣味嗜好は、おそらく変わると思うのです。趣味がずっと同じ人もいるし、コロコロ変わる人もいる。パターンが色々あります。状況も色々変わるので、これがひとつの解ですというのはないですが、今その人がどう思っているか、なにをやりたいと思っているのかは明示的にフィードバックをもらわないとわからないのです。ワンタイム聞いたらその人のすべてがわかるわけではない。その人も時間の流れと共に変わっていきます。ですので、常に対話をしていくということです。
なにかをやった時に、どういうことに対して反応が良いかということもそうです。行動がどう変化しているかというのもあります。そういうことを確認して、その人の今の価値観、やりたいことはこういう方向のようだ、ということがだいぶ見えるわけです。
例えば、同じタイプのセミナーには出ないで色々なカテゴリのセミナーに参加する人もいれば、同じ栄養系のものばかり選ぶ人もいます。この人のパターンが今の瞬間値としては読めるのです。
色々なパターンのセミナーを選択している人には別なセミナーがあった時に別のカテゴリのセミナーを積極的に紹介し、栄養系を選ぶ人には新しい栄養系のセミナーが始まる時に紹介します。といった個別化された情報提供が可能となります。
もちろん、健康診断結果とか、その人の趣味嗜好だけでない部分でもアプローチしています。
Q:構想したことが、かなり実行できている段階ですか?
A:いいえ、まだ第一歩を今やっている段階ですね。本当にこれで効果が出て、皆さんから「俺が欲しかったデータだ」、「俺が欲しかった情報だ」などのフィードバックまでは来ていませんから。
この活動も、ロングレンジで結果を見ていかないといけないので、この3年間はある程度ベースとなる部分にアプローチしてきました。それによって、どう変化しているのかを観察しているところです。
やっと少しですが、この人たちがどういう風な傾向があり、健康度、行動がどうなるのかわかってきつつあるところです。
傾向がわかるから、この人をどう理解して、この人に今から必要なものはなにかを議論できるようになってきました。
Q:かなり個別性が高いアプローチだと思いますが、数千人規模の従業員を見ていけるものですか?
A:個別性は高いですが、そんなにパターンは多くないです。環境は別としてですが、どういう風に行動しているかというパターンはそんなに多いわけではないのです。
例えば、先ほどのセミナーの選択でも、同じものばかり選んでいるか、違うものばかり選んでいる、ランダムでやっているかなど、セミナー参加にしたってそのくらいのステータスしかないわけです。
ただし、掛け算すると膨大なパターンになります。その人の健康度の傾向がどっちに向かっているか、健康度といっても肥満なのか、血糖の問題なのか、血圧の問題なのか、それだけ見たって色々な組み合わせが出きるわけです。どこに重みを置くかですね。
主眼として今はセミナーをどのような人に提供しようかと、目的論が最初にあるんです。その目的論で見た時にその人の一番重要なファクターは何か? どのデータのカテゴリを見ると一番的確かとなると、まずはセミナーの選択傾向となります。
もちろん、その手前側でものすごく特化したものだったら、その人の血糖値がどうとかフィルターをかけます。具体的にやっていくとそんなに難しくないです。
Q:なるほど、見方の問題ですね。あとはそれをどのような結果として結びついていくかを見ながら、精度が上がっていくようなイメージですね。
A:そうです。オファーした時に選択するかしないかなんて、わかるわけないですから。選ばれなかったことで、この人は、今これじゃないんだという情報がプラスされるわけです。
人という集団はある時点で固定されるわけではなく、常に変わっていく集団なので環境も変わるし、考え方も変わる。もちろん体自体も変わる。そのように変わっていくものだという前提に立つべきなのです。
健康にまったく関心のない人でも、次の瞬間になにかに気づいて、ものすごく健康にやっていこうというモチベーションの高い人に変わっていくかもしれないのです。
そういうことをちゃんと考慮した情報提供の仕方、データの見方、分析の仕方をしていかないと間違ってしまうと思います。
これはもっともっと具体的に落とし込んでいけば、誰に提供しようかなど、そんなに考えずにできるようになってくるはずです。
ですので、健康経営はデータを蓄積した後でない限りは、効果的な施策を打つことはできないと言えるのです。
Q:ステップがあるわけですね。
A:そうです。スタートした時点から全部わかっているなんてことはあり得ないので、情報を得るための行動を仕掛けないと始まりません。
それを何年かやった後で、「うちにはこういうのが必要だよね」「この人にはこういうことだよね」という話しを初めてできるようになります。一朝一夕じゃないということです。
Q:これらの取り組みにより、経営的にも結果が出たわけですが、構想段階から考えると6~7年かかっています。会社としても、どうなるかわからないところで時間をかけて投資してきたことになりますが、結果が出た今、社長はどういうコメントを浅野さんにしているのですか?
 A:「まだまだだな」と。経営者は欲張りなのです(笑)。
A:「まだまだだな」と。経営者は欲張りなのです(笑)。
私は社長と遠い関係ではないので、茶化したことも言われますが、経営の方針で実行していることもあり、皆さんやっていて良かった、と言ってくれますね。
このような活動は、いくらやっても褒められないと思ってやるしかないと考えています。ゴールを決めてしまうと進化がなくなるのです。健康の話しも絶対ここで終わりってことはないのです。
教育と同じで、ある程度教育するとその人が昔の教育する前の人と違う人になっているわけです。人間は常に考えて進化していきます。ということは終わりがないんですよ。
【プロフィール】株式会社フジクラ 人事部 健康経営推進室 浅野 健一郎 氏
 1989年藤倉電線株式会社(現株式会社フジクラ)に入社。光エレクトロニクス研究所(現光電子技術研究所)に配属され光通信システムの研究に従事。主に受動型光部品、基板型光導波回路、白色LED、光インターコネクションの開発を経て、2011年よりコーポレート企画室ヘルスケア・ソリューショングループを立ち上げグループリーダー、2014年より人事・総務部健康経営推進室副室長。2016年8月よりフジクラ健康保険組合健康推進部長を兼務。経済産業省次世代ヘルスケア産業協議会 健康投資WG専門委員
1989年藤倉電線株式会社(現株式会社フジクラ)に入社。光エレクトロニクス研究所(現光電子技術研究所)に配属され光通信システムの研究に従事。主に受動型光部品、基板型光導波回路、白色LED、光インターコネクションの開発を経て、2011年よりコーポレート企画室ヘルスケア・ソリューショングループを立ち上げグループリーダー、2014年より人事・総務部健康経営推進室副室長。2016年8月よりフジクラ健康保険組合健康推進部長を兼務。経済産業省次世代ヘルスケア産業協議会 健康投資WG専門委員
『ヘルスケアIT 2017』にて健康経営に関する基調講演
2017年4月19日(水)~4月21日(金)東京ビックサイトで開催される「ヘルスケアIT」にて、
『これからの健康経営を牽引するモバイルヘルス』
基調講演を4月20日(木)A会場にて、13:00より開催します。
浅野氏より、健康経営を導入したことによりどのように社員が変化し、収益が改善したのかをご紹介いたします。
13:00~13:30
モバイルヘルスの成功要因(海外事例紹介)
株式会社スポルツ 渡辺武友(mHealth Watch)
13:45~14:35
株式会社フジクラの健康経営による効果
株式会社フジクラ 浅野健一郎
14:50~16:20
動かない従業員を自ら行動させる!モバイルヘルスによる新たなアプローチ
モデレーター:渡辺武友、浅野健一郎
プレゼンター:ドコモ・ヘルスケア株式会社、帝人株式会社、ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社、キーウェアソリューションズ株式会社、株式会社ウィット
講演をご聴講されるには事前登録が必要になります。
上記3講演が一連のテーマとなりますので、3講演へのお申込みをお願いします。
来場登録を行い、セミナープログラムページより3講演にチェックを入れて「お申し込み」に進んでください。
人数制限がありますので、お早めにお申し込みください。
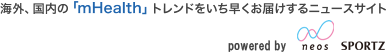



Comments are closed.