гАОmHealth WatchгАПгБІгБѓгАБгБУгБУжЬАињСгБІеЕђйЦЛгБХгВМгБЯгГЛгГ•гГЉгВєгБЛгВЙгАМж≥®зЫЃгГЛгГ•гГЉгВєгАНгВТгГФгГГгВѓгВҐгГГгГЧгБЧгАБзЛђиЗ™гБЃи¶ЦзВєгБІиІ£и™ђгБЧгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ
дїКеЫЮж≥®зЫЃгБЧгБЯгГЛгГ•гГЉгВєгБѓгБУгБ°гВЙпЉБ
пЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭ
вАЬз†Фз©ґпЉЪгГ°гГЗгВ£гВ±гВ§гГЙгБЃжВ£иАЕгАБгВЂгГГгГЧгГЂгАБеЃґжЧПгБѓгГЖгГђгГШгГЂгВєгВТзґЩзґЪгБЩгВЛеПѓиГљжАІгБМдљОгБДвАЭ
 JMIRгБЂжО≤иЉЙгБХгВМгБЯз†Фз©ґгБЂгВИгВЛгБ®гАБз§ЊдЉЪзµМжЄИзЪДеЬ∞дљНгБЃдљОгБДгВ∞гГЂгГЉгГЧгБЃжВ£иАЕгАБгВЂгГГгГЧгГЂгВДеЃґжЧПгБЂгВµгГЉгГУгВєгВТжПРдЊЫгБЩгВЛгВїгГ©гГФгВєгГИгБѓгАБCOVID-19жДЯжЯУзЧЗгБЃгГСгГ≥гГЗгГЯгГГгВѓеЊМгБЂгГЖгГђгГШгГЂгВєпЉИйБ†йЪФж≤їзЩВпЉЙгВТзґЩзґЪгБЩгВЛеПѓиГљжАІгБМдљОгБДгБУгБ®гБМгВПгБЛгБ£гБЯгАВ
JMIRгБЂжО≤иЉЙгБХгВМгБЯз†Фз©ґгБЂгВИгВЛгБ®гАБз§ЊдЉЪзµМжЄИзЪДеЬ∞дљНгБЃдљОгБДгВ∞гГЂгГЉгГЧгБЃжВ£иАЕгАБгВЂгГГгГЧгГЂгВДеЃґжЧПгБЂгВµгГЉгГУгВєгВТжПРдЊЫгБЩгВЛгВїгГ©гГФгВєгГИгБѓгАБCOVID-19жДЯжЯУзЧЗгБЃгГСгГ≥гГЗгГЯгГГгВѓеЊМгБЂгГЖгГђгГШгГЂгВєпЉИйБ†йЪФж≤їзЩВпЉЙгВТзґЩзґЪгБЩгВЛеПѓиГљжАІгБМдљОгБДгБУгБ®гБМгВПгБЛгБ£гБЯгАВ
з†Фз©ґгБІгБѓгАБ2021еєі1гАЬ4жЬИгБЂгБЛгБСгБ¶гБЃжЩВзВєгБІгГЖгГђгГШгГЂгВєгВТеИ©зФ®гБЧгБ¶гБДгВЛз≤Њз•ЮеМїзЩВеЊУдЇЛиАЕгВТеѓЊи±°гБЂгАБи®ЇзЩВеЖЕеЃєгАБгГЖгГђгГШгГЂгВєгБЄгБЃзІїи°МгВДеИ©зФ®гБЃзµМй®УгАБеИ©зФ®иАЕгБЃзЙєеЊігБ™гБ©гБМи™њжЯїгБХгВМгБЯгАВ27еЈЮгБЛгВЙеРИи®И114еРНгБЃгВїгГ©гГФгВєгГИгБМеЫЮз≠ФгБЧгАБгГСгГ≥гГЗгГЯгГГгВѓеЙНгБЂгГЖгГђгГШгГЂгВєгВТеИ©зФ®гБЧгБЯгБУгБ®гБМгБВгВЛгБ®з≠ФгБИгБЯгБЃгБѓеНКжХ∞дї•дЄЛгБ†гБ£гБЯгАВ
з†Фз©ґиАЕгБЂгВИгВЛгБ®гАБеЬ∞жЦєеЗЇиЇЂиАЕгАБи˕庳屧гБ®йЂШ隥иАЕгАБгГ°гГЗгВ£гВ±гВҐгБЃеѓЊи±°иАЕгАБжАІеИ•гВДеЃЧжХЩдЄКгБЃгГЮгВ§гГОгГ™гГЖгВ£гГЉгБ®гБДгБ£гБЯжВ£иАЕгБЃеЙ≤еРИгБМйЂШгБДгВїгГ©гГФгВєгГИгБїгБ©гАБгГСгГ≥гГЗгГЯгГГгВѓеЊМгВВгГЖгГђгГШгГЂгВєгВТеИ©зФ®гБЧзґЪгБСгВЛеВЊеРСгБМгБВгВЛгБУгБ®гБМгВПгБЛгБ£гБЯгАВ
гАМжЬђз†Фз©ґгБЃзµРжЮЬгБѓгАБгБВгВЛгВ∞гГЂгГЉгГЧгБЃжВ£иАЕгБМгГЖгГђгГШгГЂгВєгБЃжБ©жБµгВТеПЧгБСзґЪгБСгВЛеПѓиГљжАІгБМйЂШгБДдЄАжЦєгБІгАБз§ЊдЉЪзµМжЄИзЪДгБЂжБµгБЊгВМгБ¶гБДгБ™гБДдЇЇгАБгГ°гГЗгВ£гВ±гВ§гГЙгБЃеѓЊи±°иАЕгАБгВЂгГГгГЧгГЂгВДеЃґжЧПзЩВж≥ХгВТж±ВгВБгВЛдЇЇгАЕгБ™гБ©гБЃиДЖеЉ±гБ™гВ∞гГЂгГЉгГЧгБѓгАБйБ†йЪФж≤їзЩВгБЃжБ©жБµгВТеПЧгБСгБЂгБПгБДеПѓиГљжАІгВТз§ЇеФЖгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАНгБ®гАБгБЭгБЃз†Фз©ґгБЃиСЧиАЕгБѓи®Шињ∞гБЧгБЯгАВ
гАМгБУгВМгВЙгБЃйБХгБДгБѓгАБгГЖгГђгГШгГЂгВєгБЃж†ЉеЈЃгВТеК©йХЈгБЧгБ¶гБДгВЛи¶БеЫ†гАБдЊЛгБИгБ∞гАБгГЖгВѓгГОгГ≠гВЄгГЉгБЄгБЃгВҐгВѓгВїгВєгАБдљПе±ЕгВДиВ≤еЕРгБЃеХПй°МгАБеЕНи®±гВТжМБгБ£гБЯе∞ВйЦАеЃґгБЃзґЩзґЪзЪДгБ™гГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞гБЃењЕи¶БжАІгБ™гБ©гБЂеѓЊеЗ¶гБЩгВЛењЕи¶БгБМгБВгВЛгБУгБ®гВТз§ЇгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАН
з†Фз©ґиАЕгБѓгАБеПВеК†иАЕгБМиЗ™еЈ±йБЄжКЮгБІеПВеК†гБЧгБЯеПѓиГљжАІгБМгБВгВКгАБељЉгВЙгБЃзµМй®УгБМеЕ®еЫљгБЃгБЩгБєгБ¶гБЃгВїгГ©гГФгВєгГИгБЂељУгБ¶гБѓгБЊгВЛгБ®гБѓйЩРгВЙгБ™гБДгБЯгВБгАБе§ЪжІШгБ™гВµгГ≥гГЧгГЂгВТзФ®гБДгБЯгБХгВЙгБ™гВЛз†Фз©ґгБМењЕи¶БгБ†гБ®жМЗжСШгБЧгБ¶гБДгВЛгАВ
гБЧгБЛгБЧз†Фз©ґиАЕгБѓгАБгБУгБЃз†Фз©ґгБМгАБгБЩгБІгБЂдЄНеИ©гБ™зЂЛе†ігБЂзљЃгБЛгВМгБ¶гБДгВЛгВ∞гГЂгГЉгГЧгБМгГЖгГђгГШгГЂгВєгВТеПЧгБСгВЛгБУгБ®гВТйШїгВАжљЬеЬ®зЪДгБ™жІЛйА†зЪДйЪЬе£БгВТжµЃгБНељЂгВКгБЂгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®дЄїеЉµгБЧгБ¶гБДгВЛгАВгГ°гГЗгВ£гВ±гВ§гГЙпЉИдљОжЙАеЊЧиАЕеРСгБСеМїзЩВдњЭйЩЇеИґеЇ¶пЉЙгБ®гГ°гГЗгВ£гВ±гВҐпЉИ65ж≠≥дї•дЄКгБЃйЂШ隥иАЕгБ®йЪЬеЃ≥иАЕеРСгБСеМїзЩВдњЭйЩЇеИґеЇ¶пЉЙгБЃгГЖгГђгГШгГЂгВєйБ©зФ®гБѓеРМжЩВгБЂйЦЛеІЛгБХгВМгБЯгБЯгВБгАБгГ°гГЗгВ£гВ±гВ§гГЙгБЃеИ©зФ®иАЕгБМгГЖгВѓгГОгГ≠гВЄгГЉгВДгВ§гГ≥гВњгГЉгГНгГГгГИгБЂгВҐгВѓгВїгВєгБЩгВЛжЦєж≥ХгБМгБ™гБЛгБ£гБЯгВКгАБгБЭгБЃгГЧгГ≠гВ∞гГ©гГ†гБМеЈЮгВДеЬ∞жЦєгГђгГЩгГЂгБІгБЭгБЃжІШеЉПгВТгВµгГЭгГЉгГИгБЧгБ¶гБДгБ™гБДе†іеРИгБМгБВгВЛгАВ
з†Фз©ґиАЕгБѓгАБгВЂгГГгГЧгГЂгВДеЃґжЧПгВТеѓЊи±°гБ®гБЩгВЛгВїгГ©гГФгВєгГИгБМгГЖгГђгГШгГЂгВєгВТеКєжЮЬзЪДгБЂеИ©зФ®гБЩгВЛгБЯгВБгБЂгБѓгАБгВИгВКе§ЪгБПгБЃгГИгГђгГЉгГЛгГ≥гВ∞гБМењЕи¶БгБ†гБ®жМЗжСШгБЧгБЯгАВгБЊгБЯгАБгВ™гГ≥гГ©гВ§гГ≥гБІдїХдЇЛгВТгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гАБеѓЊзЂЛгВТзЈ©еТМгБЧгБЯгВКи§ЗжХ∞гБЃжВ£иАЕгВТзЃ°зРЖгБЧгБЯгВКгБЩгВЛгБУгБ®гБМгВИгВКеЫ∞йЫ£гБЂгБ™гВЛгБ®гВВжМЗжСШгБЧгБ¶гБДгВЛгАВ
и®ШдЇЛеОЯжЦЗгБѓгБУгБ°гВЙпЉИгАОmobihealthnewsгАП2022еєі6жЬИ2жЧ•жО≤иЉЙпЉЙ
вАїи®ШдЇЛеЕђйЦЛгБЛгВЙжЧ•жХ∞гБМзµМйБОгБЧгБЯеОЯжЦЗгБЄгБЃгГ™гГ≥гВѓгБѓгАБж≠£еЄЄгБЂйБЈзІїгБЧгБ™гБДе†іеРИгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВгБФдЇЖжЙњгБПгБ†гБХгБДгАВ
пЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭ
гАОmHealth WatchгАПгБЃи¶ЦзВєпЉБ
жЧ•жЬђгБІгВВCOVID-19жµБи°МеЊМгАБгГЖгГђгГШгГЂгВєпЉИйБ†йЪФи®ЇзЩВпЉЙгБМжЬЯйЩРдїШгБНгБ®гБѓи®АгБИиІ£з¶БгБХгВМгАБдњЭйЩЇйБ©зФ®зѓДеЫ≤гВВжЛ°е§ІгБХгВМгБЯгБУгБ®гБЛгВЙеИ©зФ®иАЕгВВеҐЧеК†гБЧгБЊгБЧгБЯгАВ
з±≥еЫљгБѓжЧ•жЬђгВИгВКдї•еЙНгБЛгВЙгГЖгГђгГШгГЂгВєгБѓеИ©зФ®гБХгВМгБ¶гБДгБЊгБЧгБЯгАВжЧ•жЬђгБ®гБЃдЄАзХ™гБЃйБХгБДгБѓеЫљеЬЯгБІгБЧгВЗгБЖгАВдљПгВУгБІгБДгВЛзТ∞еҐГгБЂгВИгБ£гБ¶гБѓгАБе∞ВйЦАеМїгБЂи®ЇгБ¶гВВгВЙгБЖгБЯгВБгБЂзЙЗйБУ2гАБ3жЩВйЦУгБЛгБСгБ¶и°МгБЛгБ™гБСгВМгБ∞гБ™гВЙгБ™гБДгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВгБЭгВМгБМгГЖгГђгГШгГЂгВєгВТеИ©зФ®гБЩгВЛгБУгБ®гБІгАБеЊАеЊ©6жЩВйЦУгВТеЙКжЄЫгБЩгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгБЊгБЩгАВгБ®гБ¶гВВдЊњеИ©гБ™дїХзµДгБњгБІгБЩгАВ
гБЭгБЖгБѓи®АгБ£гБ¶гВВгАБдљУи™њгБМжВ™гБСгВМгБ∞зЫіжО•и®ЇгБ¶гВВгВЙгБЖгБЃгБМељУгБЯгВКеЙНгБ™дЇЇгБМе§ЪжХ∞гВТзЈ†гВБгБ¶гБДгБЊгБЩгБЃгБІгАБдї•еЙНгБЃгГЖгГђгГШгГЂгВєгБЃеИ©зФ®гБѓгБЭгБУгБЊгБІе§ІгБНгБ™гВВгБЃгБІгБѓгБ™гБЛгБ£гБЯгБ®гБЃгБУгБ®гБІгБЩгАВ
гБЭгБЃеЊМгАБз±≥еЫљгБЃе†іеРИгАБCOVID-19жµБи°МгБЂгВИгВКгГ≠гГГгВѓгГАгВ¶гГ≥гБЧгБЯгБУгБ®гБІгАБзЧЕйЩҐгБЂи°МгБСгБ™гБПгБ™гБ£гБЯдЇЇгБМгГЖгГђгГШгГЂгВєгБЂеИЗгВКжЫњгБИгВЛгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЧгБЯгАВзµРжЮЬгБ®гБЧгБ¶Teladoc HealthгБЃгВИгБЖгБ™гГЖгГђгГШгГЂгВєе∞ВйЦАгБЃеМїзЩВж©ЯйЦҐгБМиїТдЄ¶гБње£≤дЄКгВТдЉЄгБ∞гБЩгБУгБ®гБ®гБ™гВКгБЊгБЧгБЯгАВ
COVID-19гВВеЊРгАЕгБЂиРљгБ°зЭАгБНгВТгБњгБЫгБ¶гБНгБЯгБУгБ®гБІгАБе§ЪгБПгБЃдЇЇгБМеЕГгБЃзФЯжіїгВєгВњгВ§гГЂгБЂжИїгБ£гБ¶гБНгБ¶гБДгБЊгБЩгАВеМїзЩВгВТеПЧгБСгВЛгВєгВњгВ§гГЂгВВгВДгБѓгВКе§ЙеМЦгБЧгБ¶гБНгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гГЖгГђгГШгГЂгВєгВТдљњгБ£гБЯгБУгБ®гБІгАБдїКеЊМгВВгГЖгГђгГШгГЂгВєгВТйБЄжКЮгБЩгВЛдЇЇгВВгБДгВМгБ∞гАБгГЖгГђгГШгГЂгВєгБМдЄНдЊњгБ®жДЯгБШгБЯжЦєгВВгБДгБЊгБЩгАВ
гГЖгГђгГШгГЂгВєгБМдЄНдЊњгБ®жДЯгБШгБЯжЦєгБѓгАБдїКеЫЮгБЃи®ШдЇЛгБЃгВИгБЖгБЂгАБITзТ∞еҐГгБМеВЩгВПгБ£гБ¶гБДгБ™гБДдЇЇгАБйЂШ隥гБЃгБЯгВБITгГ™гГЖгГ©гВЈгГЉгБМдљОгБДдЇЇгВВгБДгБЊгБЩгАВ
дЄНдЊњгБ®жДЯгБШгВЛгВВгБЖ1гБ§гБЃи¶БеЫ†гБ®гБЧгБ¶гАБгГЖгГђгГШгГЂгВєгБЂйБ©гБЧгБЯгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥гВТжПРдЊЫгБІгБНгБ™гБДеМїзЩВеЊУдЇЛиАЕгВВгБДгБЊгБЩгАВ
гБІгВВгАБгБУгВМгБѓдїХжЦєгБЃгБ™гБДгБУгБ®гБ†гБ®гВВи®АгБИгБЊгБЩгАВгВВгБ®гВВгБ®ITгВТдљњгБ£гБЯгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥гБЂйЦҐгБЩгВЛе∞ВйЦАзЯ•и≠ШгВДзµМй®УгБМгБ™гБДеМїзЩВеЊУдЇЛиАЕгБМгБїгБ®гВУгБ©гБІгБЩгАВеМїзЩВгГЧгГ≠гБ†гБЛгВЙгБ®гВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥гБЊгБІдЄЗиГљгБ®гБѓгБДгБЛгБ™гБДгВВгБЃгБІгБЩгАВ
дїКеЊМгВВгГЖгГђгГШгГЂгВєгБѓењЕи¶БгБ™гВВгБЃгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВе∞ВйЦАиБЈгБЄгБЃгВ™гГ≥гГ©гВ§гГ≥гВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥гБЃзЯ•и≠ШгВДзµМй®УгВТдЄОгБИгВЛдїХзµДгБњдљЬгВКгБМгАБзЫКгАЕйЗНи¶БгБЂгБ™гБ£гБ¶гБПгВЛгБІгБЧгВЗгБЖгАВ
 гАОmHeath WatchгАПзЈ®йЫЖгААжЄ°иЊЇгААж≠¶еПЛ
гАОmHeath WatchгАПзЈ®йЫЖгААжЄ°иЊЇгААж≠¶еПЛ
憙еЉПдЉЪз§ЊгВєгГЭгГЂгГДгБЂгБ¶еБ•еЇЈгГУгВЄгГНгВєгБЂгБКгБСгВЛгГЮгГЉгВ±гГЖгВ£гГ≥гВ∞гБЂйЦҐгБЩгВЛгВ≥гГ≥гВµгГЂгГЖгВ£гГ≥гВ∞гАБдЄАиИђз§ЊеЫ£ж≥ХдЇЇ з§ЊдЉЪзЪДеБ•еЇЈжИ¶зХ•з†Фз©ґжЙАгБЃзРЖдЇЛгБ®гБЧгБ¶гАБжЬђи≥™зЪДеБ•еЇЈзµМеЦґгБЃз§ЊдЉЪеЃЯи£ЕжЦєж≥ХгБЃз†Фз©ґгВТи°МгБЖгАВгБЊгБЯгВ¶гВІгВҐгГ©гГЦгГЂж©ЯеЩ®гАБеБ•еЇЈгГУгВЄгГНгВєгГҐгГЗгГЂгБЂйЦҐгБЩгВЛеБ•еЇЈгГ°гГЗгВ£гВҐгБІгБЃзЩЇи°®гВДгАБгГШгГЂгВєгВ±гВҐITгБ™гБ©гБІиђЫжЉФгВТи°МгБЖгАВ
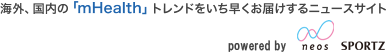



Comments are closed.