「自分達でしっかりと社員を見守れる環境づくりが健康経営への一歩」
 株式会社富士通ゼネラル 健康経営推進室 室長 佐藤光弘 氏(写真右)
株式会社富士通ゼネラル 健康経営推進室 室長 佐藤光弘 氏(写真右)
株式会社富士通ゼネラル 健康経営推進室 担当部長 石田貴久 氏(写真左)
今回の健康経営キーマンインタビューでは、今年4月から正式に健康経営推進室が設置された株式会社富士通ゼネラルに、健康経営の準備段階から、最初に取組む施策まで、導入時にスポットを当ててお話しを伺いました。(取材日:5月19日/インタビュアー:渡辺 武友/撮影:小松 智幸)
健康経営がスタートするきっかけにストレスチェックを活用
Q:健康経営推進室としてスタートしたのが今年4月とのことですが、それ以前のことから教えてください。
貴社はどのような経緯で健康経営に取組むことになったのですか?
石田貴久氏(以下:石田):1年半くらい前に健康経営への取組みがメディアに取り上げられているのを見た社長や担当役員から「自社でも検討した方がよいのでは?」との話しから始まりました。
Q:実際にスタートすることになったのはいつ頃ですか?
石田:去年の4月だったと思います。ちょうどストレスチェックをやらなければなりませんでしたので、そこに健康経営を紐付かせていけるのではないかと思い、いろいろと健康経営について調べはじめました。
調べはじめたと言っても、社内では誰も健康経営がどんなものかわかっていない状態でした。そもそも義務化されたストレスチェックもよくわからなかったのですから(笑)
ストレスチェックを進めるにあたり、まずは受託業者に話しを聞いていきました。話しの中でストレスチェックだけでなく、それを切り口にして社員の健康管理や増進をしていきましょうと提案されて、「なるほど、そうすればいいのか」とわかってきたのです。
現在、弊社の社員に関する健康情報は、すべて紙で記録しています。健診データもそうですが、産業医が相談にきた人のカルテを紙に書いて保管しています。これから健康経営をやっていくにあたり、データ化は必要だと感じました。
 Q:人事部として、従業員の健康情報を把握していたのですか?
Q:人事部として、従業員の健康情報を把握していたのですか?
石田:把握していなかったです。健保と産業医と看護師がいるので、そちらに任せていました。
今まではそれでよかったのですが、今後は、社員の健康情報(健康診断等)の見える化を行い、健康増進・保健指導が必須になってきます。健康診断の結果をロッカーから探し出してくるなんて、いちいちできないなと思いました。まずインフラを整えて、データベース化し、名前を入れればPCで過去の経歴もすぐに見られる仕組みを作らないと、川崎の本社だけでも1,500人程度いますから、とても対応できないだろうと考えたのです。
Q:インフラ整備はどのように進めたのですか?
石田:まずは事業者に見積もりを出してもらい、上司や担当役員に持っていきました。しかし、何のためにデータ化するのか、明確になっていなかったため却下されてしまいました。
Q:でも、健康経営を行うのに必要だったのではないですか?
石田:そうなのですが、弊社の規模でもシステムを入れて置き換えることになれば、費用も1,000万円からかかってしまいます。その金額に見合った価値を伝えきれなかったのです。まずはデータベース化よりストレスチェックからやれと言われました。何に使えるのかよくわからない中で、1,000万円は払えませんのでもっともな指摘です(笑)
Q:石田さんが一から健康経営をはじめるにあたり、富士通株式会社で長年、健康推進本部でストレスチェックや健康経営を担当してきた佐藤さんが指南役として出向してきたのですか?
佐藤光弘氏(以下:佐藤):そうではないです。私は人事の制度改革の業務をするために来たのですが、今では健康経営をやっています(笑)
私が赴任したのは昨年6月21日だったのですが、7月中頃に石田くんが戦略的健康管理をやりたいというレポートを作ってきました。正直、一生懸命考えているなと思いましたね。しかし、ストレスチェックは11月までにやらなければなりませんでした。そんなこと言っている場合ではない。これはただ事ではないなと(笑)
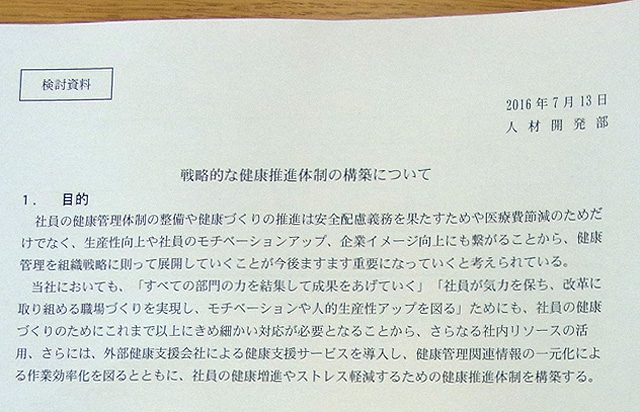
Q:まずはストレスチェックですよね?取り急ぎ、どこかの業者を選んで行ったのですか?もともと富士通本社でもストレスチェックのシステムはあるわけですから、そちらを使うとの選択肢もあったのですか?
佐藤:もちろん業者でやることも検討したのですが、半端にストレスチェックだけやると割高になってしまう。富士通のものも検討しましたが、かなり作り込んであるシステムなので費用もそれなりに高いのです。
今はそこまでのものは必要ではなかったので、今回は自分で作ることにしました。
Q:えっ!? 作っちゃったんですか?
佐藤:はい(笑)。私は富士通のシステムエンジニア会社の人事総務部にいたので、自分でプログラムを作ることもできます。毎年、学会などで発表しているプログラムがあるので、それを一部カスタマイズして、チェック項目を入れて従業員がウェブ経由で回答してもらうものにしました。
Q:それを使って、海外にいる従業員も含めてストレスチェックを実施したのですか?
佐藤:そうです。誰にも言ってないですが、夏休みと週末を返上して私が作りました(笑)
Q:石田さんは、佐藤さんがストレスチェックのことに詳しく、取組んでいたこともご存知だったのですか?
石田:はい。富士通の健康推進本部で統括部長だった方が来るとは聞いていました。
ただ、そのときは健康経営推進室もないですし、人事の制度改革をするために来ると聞いていたので、最初からやってもらおうとは全く思っていなかったです。それで7月になってから相談したら、あまりにも何もやっていないことに業を煮やしたのか、「俺がやるしかない!」となり、ご自身でやっていただいたのです。
佐藤さん、ありがとうございました(笑)
 Q:ストレスチェックではデータの収集だけでなく、分析もありますよね!? それも開発したのですか?
Q:ストレスチェックではデータの収集だけでなく、分析もありますよね!? それも開発したのですか?
佐藤:分析して帳票を出すまでのプログラムは簡単にできないので、チェック項目57に+20の設問で77項目を取得できるシステムを作って、そのデータを富士通にCSVで転送し、分析したものを戻してもらったのです。
これでようやく法律上の問題をクリアしたわけです。しかし、ストレスチェックだけでは本人の気づきまでになってしまいますので、健康経営に向けて組織としてどうなっているかの観点で評価し、現状を経営幹部、各所属長に報告しました。
そして、ある部署はチーム内でストレスを感じているようなので、どうやって職場を活性化したら良いかなど、具体的な対策を検討しているところです。
Q:今回、佐藤さんが主導的に進めてくれたわけですが、石田さんはそれを見ていてどう感じたのですか?
石田:健康経営に向けた企画書を書きましたが、実はよくわかっていませんでした。何のために社員の健康を考えるべきなのかなど、今回佐藤さんと一緒に取組んでみて段々わかってきました。
担当役員に対して健康経営をどうしていくのか、それなりに説明しているつもりでしたが、聞いている方からすると「だから何?」ということにしかならなかったのだと思います。
大元のコンセプトなり、考えなりをしっかり持って説明しなければ理解もしてくれないし、「うん」とは言ってくれないのだとわかってきました。
Q:それは、ストレスチェックの分析から具体的な課題などが見えてきたことで、イメージできてきたということですか?
石田:そうですね。結果を見て、この課題をどうするかと話す中で、社員の健康がこういうところに影響して来るということを具体的に理解していくことができました。
Q:現状が理解できると、今度は課題ごとの対策が必要になりますね?
石田:ストレスチェックの結果をもって組織分析して、フィールドワークもして、それを活かしていこうとなったとき、今の人材開発部(人事)という中だけでは、やろうと思ってもできないのです。人材開発部には、すでに取組まなければならないテーマも複数ありますので、片手間ではできないんですね。また「人事が何かやりはじめた」的なところから一歩進めないと、社員に理解してもらうのは難しいとも思いました。
それで社内外にもわかるような組織として、健康経営推進室が必要だろうとなったのです。
Q:それは現場の方としての意見であって、上の方々に了承を得て行かなければならないですよね?
佐藤:ストレスチェックが終わったのが12月なので、1月に全幹部社員に組織評価を報告し、その反応も踏まえて、2月には社長に「健康経営推進室というしっかりした立ち位置で、まずは対外的な健康銘柄ではなく、足元の基本となる産業医と産業保健スタッフを揃えたり、人事の中でも衛生管理者は石田くんしかいない状況であったりを改善しなければ動いていきません」と伝え、健康経営推進室を作って少し人を入れてはどうですか?と話しをしましたら「やれるかおまえ?」と言われたわけです。
私は今年の3月末で、富士通の健康経営推進の担務が外れてこちらに専任することになったので、状況的に取組めるようになりました。
Q:昨年6月にいらしたときは兼任だったのですか?
佐藤:富士通の健康経営も私が担当していました。富士通の方は、ある程度健康経営での対応が3月に終わりになり、富士通ゼネラルが主務になりましたので、社長にやれますと伝えました。
では早速やろうとなりまして、2月には石田くんが新しい組織を役員会議にかけ、正式に承認されました。
でも組織作っても私と石田くんしかいない(笑)
経営者の想いが健康経営を動かす原動力になる
 Q:2月に話しをして、4月にはもう立ち上がったのですか?
Q:2月に話しをして、4月にはもう立ち上がったのですか?
佐藤:やはり社長が「社員の健康を一番に考えなさい。社員とその家族の健康より大事なものは会社にはない」と幹部社員向けの定例会などで話してくれたのは大きいですね。
社長は去年の夏くらいから、そのようなメッセージを発信されていました。私も健康経営を富士通でやっていましたから「佐藤くん教えてよ」と言われて、富士通でどのようなことをしているのか伝えました。
Q:社長からのメッセージは大きいと思いますが、 健康経営によってどうなるか誰もわからないことなので、他の役員の方など、簡単に受け入れて賛成とはならないと思うのですが、どういうきっかけで理解してもらえたのですか?
佐藤:ストレスチェックの結果を全幹部社員にフィードバックしたときに、社長が、“人を思い活かす経営”の推進強化について全幹部社員に話しました。人間力を高めるために「働き方改革」「健康経営」を導入すると。ダイバーシティとかで語ってしまうと、自分達にとっては遠いイメージだったものが、経営幹部にとって近い存在になったのだと思います。
驚いたのが、こちらからストレスチェックの結果を報告に行く前に、社長自ら結果がどうなっているのか聞きに来たことです。社長や副社長は、どういう組織状態なのか知りたかったようです。
二人とも各組織の状態はだいたい見えているんですね。どういう仕事内容で、どういう上司の中で苦労しているのかなど。それが、ストレスチェックの結果を見ると、あからさまにわかるわけです。
「あの職場はやっぱりこうか。じゃあこういう風にしなくちゃいけないね」とフィードバックがもらえました。そのようなところからディスカッションがはじまり、社長や副社長と議論を深めていけたのがよかったのだと思います。
Q:ストレスチェックを長年行ってきた佐藤さんにお聞きしたいのですが、この会社ならではの気になる部分が出てきたのですか?
A:佐藤:富士通ゼネラルは8割が研究開発職、2割がSE職やデバイス開発をしている、ほぼ全員技術的研究開発職です。
総合健康リスクは全社平均では、平均的な99。140を超えたら医療スタッフが介在しないといけないのですが、富士通ゼネラルでは最高が135です。しかも21人とかなり少ない。ワークエンゲージメントの観点では、一般的に研究開発職の人は低いんです。なぜなら、例えば営業職の人は半年くらいのスパンで目標を立てて結果が見えますが、研究開発職は2〜3年越しでやっています。自分のやっていることがなかなか褒められないのです。また必ずうまくいくとは限らない職種ですから、全体では一般的な結果ではありました。
健康経営には企業に合わせたステップがある
 Q:現状で富士通ゼネラル社として目指す健康経営はどういったところになるのでしょうか?
Q:現状で富士通ゼネラル社として目指す健康経営はどういったところになるのでしょうか?
佐藤:まずは産業保健の体制を整えるところから取組みます。高リスクの社員のケアをしっかりやりたいです。今は社内の診療所に来たら対応するやり方ですが、医療職側が出向いて積極的に対応できるような体制にしようと思っています。
また「組織をいきいき元気にする」という切り口で議論しています。ワールドカフェ、グループディスカッションの仕組みを導入しようと思います。健康経営のスタッフでチームを作ってファシリテートしていきます。ディスカッションの中でそれぞれのチームがまとめて、それを発表して共感できるものを作りたいです。
経営幹部からも、組織がまとまりを持って元気になるような取組みを、健康経営推進室の一つの役割として期待されています。
Q:グループディスカッションについてどんなイメージなのか、もう少し教えてください。
佐藤:例えばですが「自分の職場で一番やりたいものは何か?」など、漠然としたテーマで コミュニケーションをとる場を定期的に持ってPDCAを回していくようなイメージですね。ポジティブに捉えられるテーマでディスカッションしてもらいます。
健康経営推進室は私と石田くんでスタートしましたが、早くも2名のメンバー(難波さん、河野さん)が加わることになりました。グループディスカッションも外部に委託するのではなく、このメンバーでやっていこうと思っています。
外部に任せて途中で関係が途切れるよりも、内部でやることで、よりよい関係作りに活かしていきたいと思っています。
Q:それをやっていく上で、健康の指標としてはどういうものを見ていくのですか?
佐藤:社員にはBMIなどわかりやすい数値の変化で見せることが必要になりますが、経営幹部には「働きがい」や「ヘルスリテラシー」がどれくらい改善されているかを報告したいと思っています。
石田:当然健康だけでなく、働きやすい、年休が取りやすい、長時間残業しないような職場にするなど、働き方改革とセットでやらなければいけないとは思っています。
Q:評価はアンケート形式で年に何度か取っていくのですか?
佐藤:そうです。ストレスチェックを年に1回やっただけでは見えてきません。もっとシンプルなものを月に1回とか週に1回とかのペースで行うことが大切になります。
このような取組みを通じて、社員の健康について経営幹部や人事のスタッフが、見ていてくれているのだなと感じてくれればいいなと思っています。
Q:フィジカルな取組みでも考えていることはありますか?
佐藤:今までは健保でもウォーキングラリーなどは開催していましたが、限られたスタッフですので外部委託が中心でした。フィジカルな取組みにおいても、自分達でやることで健康経営推進室や健保を身近に感じてもらうことが大切だと思っています。
しかし、健保も少ない人数でやりくりしながらやってきた経緯もあるので、単純に変えましょうではなく、どうしていくと社員の健康に貢献するのか、月1回打合せしながら進めていくつもりです。
Q:石田さん、健康経営をはじめますと言ったことで、幹部ではない社員の反応はいかがですか?
石田: 4月1日の組織発表を見て「何かできたな」くらいだと思います。二人とも兼務ですし。
社員には具体的な施策が動き出さないと意識されないのではないでしょうか。
会社の中で健康経営の位置づけを明確にすることが重要
 Q:健康経営はスタートしたばかりですが、これから1年2年と経過していくと結果を求められますよね!? その辺りについては考えていることはありますか?
Q:健康経営はスタートしたばかりですが、これから1年2年と経過していくと結果を求められますよね!? その辺りについては考えていることはありますか?
佐藤:初年度は、健康という切り口で社員に情報を提供するなど、社員の健康のために会社が動いているのだと感じてもらえるようにしたいと思っています。まずは「ヘルスリテラシー」を上げることなのだと思います。
具体的な行動、肥満度をどうするなどのデータを見た施策は来年、再来年になります。
まずは社員が求めたときに、健康情報が見られる、相談できるスタッフがいる、ということを理解してもらいたいです。情報の配信や社員向けのSNSを進めていこうと思います。
私も色々なところで会話しますが、人事の順位づけでは福利厚生や健康は、悲しいかな、一番うしろの方なんです。やはり人事制度とか人事評価、組織などが取りざたされます。そういった意味で専門の人が、なかなか育たないのです。
今は人事の優先順位で考えるのではなく、会社の仕組みにしないといけないとの意見をよく聞きます。健康経営推進室として立ち上げ、社員の健康の優先順位が低いことはないと、伝えていかなければなりません。
石田くんも忙しく労務担当をしながらも、戦略的健康が必要と考えています。他の社員でそういう想いを持っている人は何人かいるので、もっと増やしていくことがサスティナブル経営だと思うのです。
Q:今後、佐藤さんが富士通時代にやってきた経験をどう活かす(メンバーに注入していく)のですか?
佐藤:私は長年、人事も健康も両方やってきましたから、両方の立ち位置がわかる。どちからも大事なのです。
多くの企業では、人事が健康に取組むのはこれからで、わからないことも多い。そこで大切になるのが外部で意見を共有できたり、アドバイスし合えたりする人間関係です。これは私にとっても財産です。フジクラ社の浅野さんもそうですし、こうやって話しができる渡辺さんもそうです。大学の先生方も、もちろんそうです。
どうしても人事のスタッフはクローズした世界で仕事をしてしまいますから、そういった人間関係が作りにくいのです。色々な所に行って吸収し、広く人のつながりを作ってほしいです。私はそれを伝えるのが役目かなと思っています。
 石田:今、会社で健康経営とか社員の健康について語れるのは佐藤さんしかいないんです。みんなが勉強をしていかないといけない、経営者も社員も我々も。
石田:今、会社で健康経営とか社員の健康について語れるのは佐藤さんしかいないんです。みんなが勉強をしていかないといけない、経営者も社員も我々も。
これから勉強を始める段階で、本当に入り口のところです。勉強しないと何で健康が大事なのか、何となく大事だと思っているけど、それが経営に直結するのか、ほとんどの人が理解していないのです。しかし、こういう人が社内講師をして、ことあるごとに伝えていくということが必要になりますので、我々も理解・勉強していかないといけないのだと感じています。
Q:健康経営をやってこれだけ儲ける。といきなりいくことよりも、まずはベース的なところを見直して、石田さんがおっしゃったようなところとして、まずそれがどのような効果があるか自分たちで実感してみようと、はじまったところですね?
佐藤:そうです。最初の一歩です。
健康経営は何からはじめてよいのかわからない方が多いようですが、そもそも業務の片手間でやるのは難しいです。やっていけば常に新たな課題も出てきますので。
何より想いを持った人がいないと進めていくことはできません。弊社でも同じで、私も何年かすればいなくなるわけで、そのときに、その想いを受け継いでもらって“根付かせている”かが重要になります。社内の人を育てていくという感性でいかないとならないと思います。
石田:このような取組みは、やはり会社が順調な時でないとできないことだと思います。人への投資ですから。会社の業績が順調でないと意識が向きません。
弊社は、2000年前半から2010年くらいまで厳しい時代が続いて、利益確保を最優先で頑張ってきました。正直、その当時は、健康や社員を活かす経営という余裕が持てなかったのです。
他社に比べると、社員を活かす健康に対する投資が後回しになっていた。気づけば社員が疲弊している。なんとなくモチベーションが低いような気がする。元気がないような気がする。
これはまずいと、やっとそこに目がいくようになったのがここ最近だと思います。
そこに佐藤さんが来て、タイミングが重なり、経営幹部がそういう気持ちになったのでやれるようになったわけです。できるのは今しかないのです。
Q:会社によっては、今すぐやった方がよいことではない場合もあるんですね?
石田:そうだと思います。富士通ゼネラルは上場している会社ですし、現在は健康に対する投資をするだけのベースを持てていますが、そうでない状態や規模の企業によっては、健康への投資より優先することがあるでしょうし。そんなことしていたら仕事ができなくて会社の存続にかかわる!なんてことにもなりかねませんから。
Q:最後に、これから健康経営に取組もうと考えている方にアドバイスをお願いします。
佐藤:昨日、浅野さんと渡辺さんからお声がけいただき、ウィットさんで開催された人事部、健保の方が集まるフォーラムに参加させていただきました。このような健康経営ですとか、同じ想いを持っている人でネットワークを作って、フランクに会話できるような関係を作ること自体が大切なことです。もっともっと活発にできたらいいですね。
人事の情報だと出せないことも多いですが、健康だったら色々な施策、どんなことをやっているの?とか、少し敷居が低いので共有できます。共有するだけでもよいと思うので、率先して参加するとよいと思います。
Q:ありがとうございます。ウィットさんでのフォーラムは次回8月に開催します。佐藤さんもぜひ参加してください。
今後の貴社の経過も見させていただければと思います。今後とも宜しくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
 【プロフィール】
【プロフィール】
株式会社 富士通ゼネラル 健康経営推進室 室長 佐藤 光弘 氏(写真中央)
1984年富士通株式会社に入社。99年沖縄富士通システムエンジニアリング総務課長、2004年に富士通に復職し、マーケティング本部人事部担当部長として、当時のSEに働き方改革・構造改革に従事し、2008年健康推進本部健康事業推進統括部長として、富士通グループ全社員の健康推進体制の構築、2012年東京大学大学院医学部・日本生産性本部共同設立の「健康いきいきづくりフォーラム」設立準備会メンバーとして参画、2016年4月株式会社富士通ゼネラル人材開発部主席部長として出向、現在に至る。
株式会社 富士通ゼネラル 健康経営推進室 担当部長 石田 貴久 氏(写真左)
2000年株式会社富士通ゼネラルに入社し、法務部に配属。社長室勤務を経て、2012年から人材開発部。労政担当として、現在は長時間労働抑制、生産性向上などの働き方改革を推進。2017年4月から健康経営推進室を兼務。
(写真右は新メンバーの難波美智子さん)
『ウェルネスフードジャパン』にて健康経営に関する基調講演
2017年7月25日(火)~7月27日(木)東京ビックサイトで開催される「ウェルネスフードジャパン」にて、
『これからの健康経営を牽引するモバイルヘルス(食改善編)』
基調講演を7月25日(火)会場Oにて、13:00より開催します。
13:00〜15:30
モバイルヘルスを活用した継続利用促進事例紹介
株式会社スポルツ 渡辺武友(mHealth Watch)
職場の活性化に向けて
株式会社富士通ゼネラル 佐藤光弘
食から改善するモバイルヘルスによる新たなアプローチ<パネルディスカッション>
モデレーター:渡辺武友、佐藤光弘
プレゼンター:株式会社ウィット天辰次郎、Noom Japan 濱嵜有理、ドコモ・ヘルスケア株式会社 戸田伸一
人数制限がありますので、講演をご聴講される方は事前登録をおすすめします。事前登録は7月16日までとなります(以降は当日会場申込み)。
お申込みはこちらからお願いします。
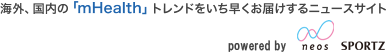



Comments are closed.