
「スマートフォン社会の到来が、mHealth普及へのターニングポイントになる」
青森公立大学経営経済学部 准教授、ITヘルスケア学会 理事 木暮 祐一 氏
「mHealth」に関して世界的に注目が集まっているが、まだ日本では、全体観を把握し、今後どうあるべきか分析できている人は少ない。mHealth Watch初となるキーマンインタビューでは、医療、予防そしてモバイル市場を俯瞰して見ている方にお話しを伺いたいと思っていた。 そのようなタイミングに、医療、モバイル業界に精通し、現在、青森公立大学を中心に研究・教育活動を展開する木暮祐一氏にお話しを聞かせていただいた。(取材日:6月26日/インタビュアー:渡辺 武友/撮影:小松 智幸)
日本の医療業界のモバイル(スマートフォン)活用はこれから
『木暮祐一さん』と聞いて最初に思い浮かべるのは『アスキーにいたケータイコレクター』と思うのは私だけだろうか? 木暮さんはガジェット好きには有名で、80年代から携帯電話業界をウォッチし、1,000台を超えるケータイをコレクションしている方だ。一方、ITヘルスケア学会の理事を務め、モバイルヘルスケアシンポジウムの実行委員も務めるなど、モバイルから医療分野まで精通しているという、少々“珍しい経歴”をお持ちの方だ。
まずは、その経歴から伺った。
「出身大学は杏林大学で、保健学を勉強してきました。卒業後、最初に務めたのが(株)法研で、健康関連の情報提供をする媒体に携わっていました。一方、学生時代に自動車関連のアルバイトをしていく中で、黎明期の自動車電話、携帯電話サービスに出会い、この“どこでも通信できる環境”というものに個人的に可能性を感じまして、趣味の一環で携帯電話関連の情報収集、端末のコレクションをしていました。
2000年に、(株)法研から(株)アスキー(現アスキー・メディアワークス)に移ってからは、携帯電話関連の媒体を手がけるようになりました。このときはヘルスケアとモバイルが結びつくとは想定していませんでしたが、時代の流れで医療業界でも『通信』の活用が求められるようになり、中でも“いつでも通信できる”、“誰でもが持ち歩いている”というモバイルならではの特性が救急医療分野や日常の生体情報収集などに活用できるのではと、注目されるようになっていったのです。
こうした中で、医療とIT(モバイル)の組み合わせに新たな可能性を感じ、2004年に徳島大学大学院に入り直し、携帯電話を遠隔医療に応用するアプリケーション開発に取り組んできました。その後は医療分野に通信を活用するところを掘り下げて行きたいと思い、各所で遠隔医療に関わる研究に携わるようになったのです」
当時は医療とモバイルというと、ある種『異色』な組合せであったであろう。医療分野にも、かなりITが浸透したことから、昨今ではモバイルの導入もスムーズにいっているのだろうか?
「そんなことはないです。携帯電話は電磁波を出すからと、医療の現場では嫌われてきました。モバイルはともかくも、情報通信の普及は目覚ましいです。しかし、残念ながら医療側とシステムを構築する情報工 学側がうまく意思疎通できているかというと、まだまだ不十分と感じます。
学側がうまく意思疎通できているかというと、まだまだ不十分と感じます。
一部を除いて医療側の先生は、情報通信側の動向を十分に追い続けられない状況がありますし、情報工学側の方々にとっては未だに医療は壁が高い領域で、医療分野に求められるニーズを正しく拾いきれていない状況です。
医学と情報工学の相互の研究者や開発者が意思疎通でき、お互いに理解しやすくなる場をいろいろな形で作りたいと思っています。業界団体における研究会活動や、ITヘルスケア学会をはじめとする学会活動がその一環で、こうした所が、いろいろな立場の方々が相互に意見をぶつける場になったら良いなと思っています」
海外ニュースでも伝わっているように、アメリカでは医師の7割がスマートフォンやタブレットを活用しているという。日本の医療現場はどうなのだろうか?
「日本の医療現場ではPHSで通話を主体とした緊急通信手段が普及していています。スマートフォンをプライベートで使う先生は増えましたが、スマートフォンを活用できる環境を目指すのであれば、院内で活用する通信手段もスマートフォンにしていくことが望ましいでしょう。ただし、新しいものを取り入れたい先生はスマートフォンにシフトしています。OSではiOSの方が多いように感じています。
どう活用すると便利なのかという訴求が、日本で十分できてなかったので、モバイルヘルスシンポジウムやITヘルスケア学会でスマートフォンの具体的な活用事例を紹介しています。徐々にですが、先生達の間にも広まりつつあるように感じています。
日本ではスマートフォンはおもちゃ的な感覚もあります。『通話ができるコンピュータ』という認識で捉えていくと、利用範囲が広がってくるはずです」
医療情報は誰のためのもの?
モバイルに限らず、ITが病院内に浸透していくためには、他にどのようなことが必要なのだろうか?
「電子カルテなど見ていると、システム開発には当然医療の現場で求められる要件に詳しい方が関わっているはずですが、実際の運用においてはもう少し痒いところに手が届くようなカスタマイズが求められます。病院によって、そういったニーズは違ってくるので、同じものをどこでも使うのはなかなか難しいでしょう。
これからは、大きな医療機関や組織では、院内に情報システムや開発部門を持っても良いのではないでしょうか? それぐらいしないと、本当に現場で使いやすい医療と情報の連携はできないような気がしています。
電子カルテシステムはここ20年ぐらいで急速に普及してきて、利用が一般化してきたのは、約15年です。医療の分野にしてみれば新しい世界ですが、そのオペレーションを含めて、どういう在り方が必要か考えるタイミングではないかと思っています」
日本では『どこでもmy病院構想』が打ち出されている。電子カルテもその一端を担う機能だ。しかし、20年も前から導入が始まっているにも関わらず、なぜ身近に感じることができないのだろうか?
「残念ながら、『入力した情報の活用』ができていないのが日本の現状です。電子カルテの例だと、病院のオペレーションは電子化されたように見えるが、最後会計の書類は処方箋という紙になって出てきます。その紙を持って薬局に行って、薬局でもまた情報を入力している。1回入力した情報をいかに活用していくか が重要です。
が重要です。
韓国に視察に行くと、住民登録番号(国民共通番号)があり、それが記録された身分証明書があるので、保険情報や病院の診察券など、あらゆる情報が自分のIDに紐づいて活用されているのです。病院に行く時には、診察券も不要です。自分の身分証明で必要な情報が出てくる仕組みです。 情報は患者さん自身のものです。
患者さんが便利なように活用できないと意味がないと思います。例えば、他の病院に行って、自分が別の病院に蓄積している電子カルテの情報など、他の病院でも活用したいと考えるのは、患者さん自身の問題なのです。
電子カルテを含む健康情報が誰のものなのか? 当面注目すべき議論のテーマになると思っています。そして間違いなく『入力した情報の活用』には向かっています」
予防、医療業界が連携し価値あるサービス化へ
次に予防としてのモバイルヘルスの活用について伺った。木暮さんから予防市場はどのように見えているのだろうか?
「日本は国民皆保険制度のため、誰でも保険に入れて、いつでも自己負担3割で医療を受けることができます。一方、アメリカは自由保険なので、自分自身が健康を管理しないと保険料にも影響してきますし、リスクが高いと保険も入れないような状況になる場合もあります。そのため、健康管理を自分自身でする必要があるとの認識があります。その認識の差が実は大きいのでしょう。 日本では、例えば通信キャリアが健康系のコンテンツサービスを作っていますが、利用率は高いとはいえません。やはり、国民自身がそれほど健康に関心を持っていないような状況で有料サービスを提供しても響かないのではないでしょうか?
医療費を削減したい状況ですので、本来は保険制度自体の見直しが必要なのかもしれません。万が一、アメリカのようにリスクで保険料が変わるような状況になると、自分自身でセルフケアしなきゃいけないという考え方が一気に広まって、モバイルなり、その他ITを使って自分の健康管理をする流れが一気に進む可能性もあります」
保険制度が変わらないと現状(国民の健康への意識)は改善しないのだろうか?
「切り口はいろいろあると思います。例えば『ゲーミフィケーション』が一時、話題になりました。健康系コンテンツでもエンターテイメント要素を加えたものが、ある程度利用される傾向もあります。それでも、モチベーションが高い人が使っている状況です。
もっとエンターテイメント要素を盛り込んだサービスがうまく導入されれば、知らず知らずに健康を管理されているようなサービスがこれから出てくる可能性があり、そのツールとしてスマートフォンは最適なのだと思います」
アメリカでは健康保険大手のAetnaが『CarePass』というモバイルPHRサービスで、また健康サービス会社のMyFitnessPalがアプリで、他社のデバイスやアプリと連動することで、ユーザーの利用価値を高めている。日本でも今後、自社だけでなく、他社との連携が重要になるのではないだろうか?
「まったく同じ考えを持っています。スマートフォンが中心にあり、いろいろなものが繋がって行くのが今後の世界のあり方と思っています。日本もそのようになっていく気がしています。
ただし、日本が難しいのは『囲い込みが好きな文化』だという点です。例えば『コンティニュアヘルスアライ アンス』を立ち上げる時、国内の企業から立ち上がったものの、標準化はなかなか進まなかったそうです。そこにインテルなどの米国系企業が参加することで世界で先に標準化され、これが後に日本に逆輸入されたと聞きます。
アンス』を立ち上げる時、国内の企業から立ち上がったものの、標準化はなかなか進まなかったそうです。そこにインテルなどの米国系企業が参加することで世界で先に標準化され、これが後に日本に逆輸入されたと聞きます。
日本企業のまだまだ多くは、囲い込みによるビジネスでの収益を考えてしまっているのが現状です。ビジネスモデルを否定するわけではありませんが、医療やヘルスケア分野のサービスにおいては、利益の追求よりも広くユーザー側にメリットがあるものであってほしいと願っています。閉じたサービスは、企業の利益やセキュリティ面でのメリットはあるかもしれませんが、ユーザーにとってはメリットが多いとは思いません。例えばそのサービスを辞め、他のサービスに乗り換えようとしたら全部データが消えてしまうということであれば、利用も限られてしまうのではないでしょうか?」
最後に、海外のようなmHealthによる広がりをもたらすために、どのように取り組むべきかアドバイスをいただいた。
「通信も医療もオープンにしていかないと、ユーザーにとって不利益になります。予防分野でも、いろいろな企業がオープンに繋がってユーザーのデータを有効利用できる環境を作って欲しいです。
特に通信キャリアが担う役割は大きいですが、どうしてもクローズドな世界になってしまいます。そこは予防、医療業界の側が声を大きくして、オープンなサービスを各社のスマートフォン上に標準搭載してもらうよう働きかけるべきです。
日本人には、周りの人たちが使っていると自分も使わなければ、と考える国民性があります。これをうまく活かして、誰もがスマートフォンを利用するような環境のなかで、自然に医療・ヘルスケア系のアプリやサービスを使ってもらえる環境ができると良いですね」
 【プロフィール】 木暮 祐一(こぐれ ゆういち)
【プロフィール】 木暮 祐一(こぐれ ゆういち)
1967年、東京都生まれ。出版業界、モバイルコンテンツ業界を経て、2004年に携帯電話研究家として独立。2007年には「携帯電話の遠隔医療応用」をテーマに博士(工学)の学位を取得し、大学教員に転身。現在は青森公立大学 経営経済学部 地域みらい学科 准教授を務める。青山学院大学ヒューマン・イノベーション研究センター客員研究員、徳島大学工学部、熊本大学医学部各非常勤講師兼務。モバイル学会 理事/副会長、ITヘルスケア学会 理事。
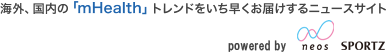



Comments are closed.