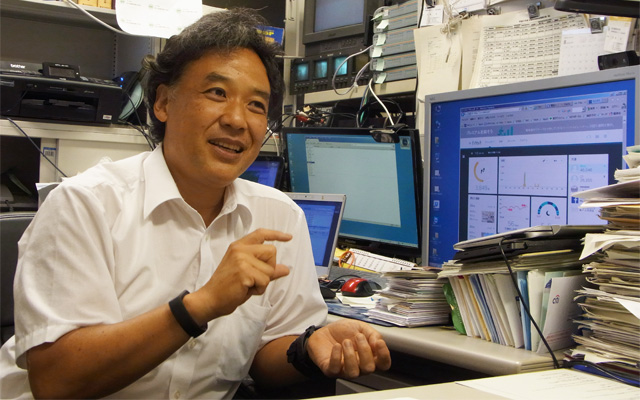 「あらゆる健康情報をオープンデータとして蓄積することで、はじめて適切な活用ができる」
「あらゆる健康情報をオープンデータとして蓄積することで、はじめて適切な活用ができる」
国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 上席主任研究官
ITヘルスケア学会代表理事
水島洋氏
今年6月に熊本で開催された『ITヘルスケア学会 第9回年次学術大会&モバイルヘルスシンポジウム2015(合同開催)』にてメディアサポートとしてmHealth Watchが協力させていただいた。今年は初めての地方開催であり、学会が一般社団法人化したことを発表した、特別な会になった。学会開催から2ヶ月が過ぎた今、なぜこのタイミングに一般社団法人化したのか?また来年10回目を迎える学会はどうなっていくのか?代表理事である水島洋氏にお話しを伺った。(取材日:8月13日/インタビュアー:渡辺 武友/撮影:小松 智幸)
健康な人の健康行動につなげるには健康指標が重要に
Q:水島先生の経歴を教えてください。
医者以外の方法で、人間の医療に役立つことをやりたいとの思いがありました。大学は薬学を専攻しましたが、薬学的なことはあまりしてこなかったです(笑)薬学は物理、科学、生物、薬理学まで範囲が広いです。私自身が幅広いことに興味を持つ方なので、1つに絞るのではなく、広い視野で活動したいことから薬学に進みました。博士までは遺伝子を専門としたので、その後は国立がんセンターにてバイオの研究を行いました。
当時、がんセンターでも今後普及するコンピュータを検討することになりました。私は学生のころからコンピュータに興味があり知識も持っていたため、このプロジェクトに携わることになりました。ウェブがない時代だったので、まずは一般に普及していなかったインターネットへの接続を行い、がんセンター紹介のホームページを作り情報提供をはじめました。厚生労働省が医療用としてはじめてスパコンを導入し、がんネットというがんセンター全体のネットワークを構築することになりました。がんネットで情報提供から、スパコンを活用した解析までできるようになりました。
その後、ゲノムセンターで遺伝子情報をどう管理するかを手がけ、ゲノムの研究も一段落ついたときに東京医科歯科大学に移り、オミックスというゲノム以外にも大量の情報を処理する仕事に就きました(オミックス医療情報学教授)。オミックスとは今でいうビッグデータで、一部の情報だけでなく網羅的に集める新しいタイプの医療情報処理です。主にはがんで活用するためでした。
4年ほど前からは、難病や災害医療という違うフィールドが大事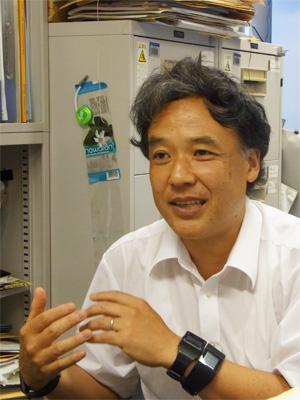 になってきているということで、国立保健医療科学院に移り、公務では難病や災害の研究を中心にやっています。
になってきているということで、国立保健医療科学院に移り、公務では難病や災害の研究を中心にやっています。
公的な研究以外の活動として、今までの経験を活かし「遺伝子解析から健康をどう測るか?」という長寿遺伝子検査を開発しました。ウェアラブルデバイスに関しても、がんセンターのころから研究を続けているので、これらを応用したライフログを活用した未病領域で健康維持について研究を進めています。
iPhone、iPadが出てきたとき、これらをうまく活用する研究会を作らなければいけないと思い、すでにはじめていたITヘルスケア学会にて2010年より、モバイルヘルスシンポジウムをスタートしました。
Q:ここ3年ほどITヘルスケア学会に参加させていただいていますが、印象として医療に寄った部分が強いように思えていました。しかし、水島先生のお話しだと、もっと健康に寄っている学会だとも感じましたがいかがでしょうか?
別の学会として医療情報学会があるので、医療的なことはそちらでやることで差別化したいと思っています。医療情報学会は、大学病院のシステムがどうあるべきかを議論し、そこに集まる情報をどう連携させるかを考えるのが主なテーマだと思います。大学病院としてはこのような議論は重要ですが、開業医や患者さん、健康な人が求めていることは違うと思います。ITヘルスケア学会は、そこにフォーカスを当てた学会にしたいと思いました。
開業医はIT情報に関して詳しい人が多いので、そのような方々の研究発表、情報交換の場を作りたいと思ったのです。
Q:健康な人のサポートをするとのことですが、「健康な人」の定義は病気でない健康な人全般なのでしょうか?
健康な人と病気な人で、明確な線があるわけではないです。健康の中でも、超健康から病気直前の人までと幅広い。そして軽い病気から重い病気へとリニアにつながっているのです。そういう意味では病院に行くまでの健康といえるでしょう。
病気に近づいたら健康状態に戻す。健康の中でもどの位置付けにいて、自分で行動を変えることで適切なポジションに戻してあげるような仕組みを提供していきたいです。
Q:健康な人を健康行動に向かわせるのはとても難しいです。研究の中で何か良い方法が見えてきましたか?
我々が開発した1つが『長寿遺伝子検査』というものです。これは病気の検査ではなく、血液から長寿遺伝子がどれくらい元気かを測定するものです。この検査で、健康な人のポジションを評価できるようになりました。
健康行動をすると長寿遺伝子の数値が上がるので、サプリを飲んだときなど、気分だけでなく数字としての評価ができるようなります。
これからは絶対的な数字(指標)を作ることが大事だと思っています。今もウェアラブルを複数付けていますが、それぞれ計測数値は違います。統一できるよう定義して、定義に基づくとどのような可能性が持てるなどの話しができるようにしたいのです。『長寿遺伝子検査』は、その中の1つとして作りました。
Q:簡易遺伝子検査では生まれ持った遺伝子による体質などが想定できますが、改善行動により数値が変わるものではありませんね?『長寿遺伝子検査』は行動により変化するものなのですか?
そうです。高校のとき習った科学を思い出して欲しいのですが(笑)、DNAとRNAを習ったと思います。DNAは親から遺伝子として受け継いだものが書かれています。長寿遺伝子検査は、血液の中にあるメッセンジャーRNAの量を測っているのです。生活の仕方で増えもすれば減りもするものなので、効果を測るのには適しています。
誤解されないために「遺伝子検査」といわない方がいいのかもしれないですね!?
検査するには、提携病院に行っていただき採血してもらいます。1回に数万円かかるので、数ヶ月に1回や年に1回程度の検査になると思います。自分なりに健康法を変えた後などに、効果の確認として検査してみると変化が見えるので自己評価ができます。
検査は一部病院の人間ドックの中でやってもらい、他の数値と合わせて見ながら、今後の予測に役立てるようにしていくようにしています。現在はデータ集めをしているところです。
Q:『長寿遺伝子検査』は数ヶ月に1回、もしくは年に1回とした場合、その間はウェアラブルで対応するのですか?
これらは全く違うデータですが、まずはいろいろなデータを取ることが大切と思っています。健康なときのデータを取ることが仕組みとしても、産業としても大事になります。健康データの集約が必要になるのです。
国内で完結する健康オープンデータ環境の整備を
Q:今年のITヘルスケア学会の評価はいかがですか?
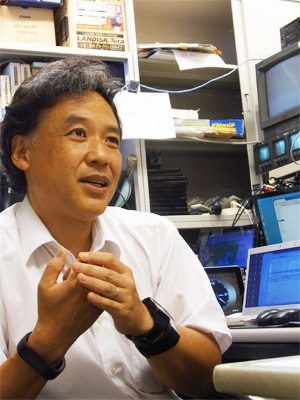 はじめて地方で開催して集客など心配していましたが、木暮大会長のお陰で、演者もよく、集客面でも納得の行く結果だったと思っています。参加者も地元の方がメインになると思っていましたが、東京などから来た方も多く、わざわざ熊本まで来るだけの価値を見出だせてもらったという点でも、とてもよい会だったと思います。
はじめて地方で開催して集客など心配していましたが、木暮大会長のお陰で、演者もよく、集客面でも納得の行く結果だったと思っています。参加者も地元の方がメインになると思っていましたが、東京などから来た方も多く、わざわざ熊本まで来るだけの価値を見出だせてもらったという点でも、とてもよい会だったと思います。
今年のポイントとしては、モバイルヘルスシンポジウムではウェブアプリケーションからロボットまで広がりが持てるようになりました。また病気ではない、健康ビジネスが成立してきたことが実感できる場になったことではないでしょうか。
やっと学会とシンポジウムの立ち位置が見えてきたように感じます。これからは増々、健康におけるITの活用が大事になってくると思います。
Q:なぜこのタイミングに一般社団法人化されたのですか?
健康に関するデータは、各社がそれぞれのサーバで管理し、しかも国外で管理されているものが多い状況にあります。今のところ集約できていません。AppleのHealthやMicrosoftのHealthVaultに集約するなど話しもありましたが、日本では制限があり、なかなか進みませんでした。
日本に集約できる場があった方がよいと以前から思っていたので、この度ITヘルスケア学会でデータを預かるサービスを立ち上げることになりました。集約するにあたり、どこか企業が独占するものであってはいけないと思っています。例えば、通信3社の緊急時の伝言掲示板はそれぞれ違いますね!?これではいざというとき利用者は困ってしまいます。内閣府が作っていくなど、顧客の囲い込みのためでない環境が必要になります。
ヘルスケアデータに関しては、国として厚生労働省や経済産業省がやるとの話しも出たことがありますが、実現に至っていません。
オープンデータ化の動きがアメリカで活発になっています。アメリカでは学会ベースで進んでいます。それならば、日本でも学会として取り組んでみてもよいと思ったのです。とはいえ、個人情報の取り扱いなど任意団体では信用も得られないので、責任がある法人になれるよう一般社団法人化しました。
医療のデータなら医療情報学会が扱えばよいですが、健康情報とウェアラブルのような生活データを統合して、健康活動を支援するような環境を作っていきたいと思っています。
Q:預かるデータはセンシングできるデータのみですか?健康ビジネスにおいては、食事の記録や気分の変化など、センシングできないものも多く含まれます。
客観的なデータであるべきとの話しもありますが、センシングできないものも必要だと思っています。
例えば、難病患者向けのポータルサイト『WE ARE HERE』の協力をしていますが、そこでは患者さんたちが研究などに役立てて欲しいとの思いからセンシングできないことも記録してもらっています。検査値などの記録はもちろん、障害に対する患者さんの工夫を共有出来る場にもなっています。そのような情報も入れるべきだと思っていますので、センシングできる情報に限りません。
Q:ITヘルスケア学会に対して健康ビジネスプレイヤーの多くは、自分と関係ない医療の学会にも見えていると思います。しかし、本来は健康ビジネスの現場を知る人達こそ参加すべきだと思っています。今後オープンデータ化を検討してく段階でも、ぜひ健康ビジネスの方々に参加してもらってはどうでしょうか?
そのように思われているとはわからなかったですね。隔たりなく一緒に作っていける場にできればよいと思っています。オープンな場にしていきたいので、ぜひ参加してアドバイスをいただきたいです。
これからは健康、予防領域の方々が面白くなってくると思っています。企業だけでなく、区や町などの自治体にも参加できる場にしていきたいです。自治体は当然ながら健診データなどいろいろなデータが集まっています。そのデータをもっと活用できるようにしていけるはずです。国としても、医療費は限界にきているので、予防に力を入れたいと考えていますので。
Q:国は予防領域の活性化のために予算を付けていくのでしょうか?
経済産業省ではビジネスとしてですが、厚生労働省でも 予防に関する予算は持っています。きちっと予算をつけた動きをするためには、成果に対して数字で見せることが重要になってきます。
予防に関する予算は持っています。きちっと予算をつけた動きをするためには、成果に対して数字で見せることが重要になってきます。
例えばウェアラブルをつけたら、その人の医療費がいくら下ります。と数字が出てくると、この商品にはいくらの価値があると明確になります。例えば、1人1万円下がるなら、数千円のウェアラブルを区民に配ることはあり得るわけです。
このような活動をするためにもデータを集めなければならないのです。自治体なら医療費のデータと比較しながら判断することもできます。
Q:国など自治体でITを活用した健康増進活動が動き出していますが、水島先生の視点ではどう評価されますか?
基本的に医療はしっかりとコントロールされ、医学的な責任体制のもとに行われるものだと思っています。医療は厚生労働省管轄で厳しく管理すべきだと思います。
一方、健康になるとそんなに制限をかけないでもっと優しく試しができてもよいのではないかと思っています。例えば、経済産業省の中にはヘルスケア産業課があるので、健康に関する所管が経済産業省でもよいとも思っています。
遺伝子解析も病気の診断や治療のためでなければ、経済産業省の領域でやってもいいと思えます。ウェアラブルに関しても、製造物責任が伴われるものはしっかりやるべきですが、そうでないものは何でも厳しいことをいうのではなく、いろいろチャレンジさせるべきだと思います。
脈拍はOKになったなら、血中酸素飽和度(SpO2)もOKにするなど、これからいろいろなセンシングができるようになるので、それらを医学的な正式な数字ではなく、「おもちゃの数字なんだ」くらいのつもりで、いろいろ試させてくれるとよいですね。
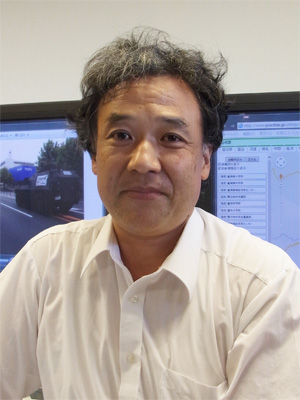 【プロフィール】:水島洋氏 国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 上席主任研究官、ITヘルスケア学会代表理事
【プロフィール】:水島洋氏 国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 上席主任研究官、ITヘルスケア学会代表理事
1960年、東京都生まれ。東京大学薬学部卒業。薬学博士。国立がんセンター疾病ゲノムセンター室長、東京医科歯科大学オミックス医療情報学講座教授を経て、現在国立保健医療科学院上席主任研究官。ITヘルスケア学会代表など兼務。専門領域はゲノム研究のほか、分子生物学や医療情報学、難病、災害など。自転車走行17万キロ以上など、詳しくは以下を参照。
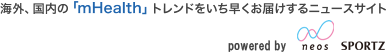



Comments are closed.