 『Real World Data Japan 2016』1日目のレポートに続き、2日目のレポートをお届けします。(取材・文:1日目・小松智幸/2日目・渡辺武友)
『Real World Data Japan 2016』1日目のレポートに続き、2日目のレポートをお届けします。(取材・文:1日目・小松智幸/2日目・渡辺武友)
セッション4
上市後にRWDを活用し、患者さんのアウトカム向上に貢献
患者さんのQOLを高めるために、RWDをどう組み合わせ、活用すべきか
慶野晋一氏(シミックホールディングス株式会社 社長室 執行役員)
 慶野氏は、「PMSとRDWをどう組み合わせ、活用することができるのか」「PMSとPROを組み合わせた試験は可能なのか?」「患者さんのQOLを高めるために、どのようなデータと分析が必要なのか?」の3つのテーマで講演を行いました。特にmHealthへの関連性が高い、「患者さんのQOLを高めるために、どのようなデータと分析が必要なのか?」についてご紹介します。
慶野氏は、「PMSとRDWをどう組み合わせ、活用することができるのか」「PMSとPROを組み合わせた試験は可能なのか?」「患者さんのQOLを高めるために、どのようなデータと分析が必要なのか?」の3つのテーマで講演を行いました。特にmHealthへの関連性が高い、「患者さんのQOLを高めるために、どのようなデータと分析が必要なのか?」についてご紹介します。
<患者さんのQOLを高めるために、どのようなデータと分析が必要なのか?>
現在は患者のQOLを高めるためのデータは十分とはいえない。臨床試験の中QOLデータを取っている例は見られるが、リアルワールドの中で取ることが望まれる。今後強化すべきところになる。
<なぜQOLデータが必要なのか?>
例えばバイエル薬品社の場合、インターネットにて、2種類の抗疑固薬(仮想的に設定したもの)のどちらを使いたいか、アメリカと日本の医師と患者に調査を行った。日本の医師は「脳卒中と出血を同程度に重視する」傾向が見られたが、患者は「機能障害を伴う脳卒中を重視する」傾向にあった。しかしアメリカの場合は医師と患者に違いが見られなかった。このような点が意義のある情報となる。患者が何を考えていて、何を選ぶかを把握することが大切になる。
次は中国の認知症に関するもの。現在、中国の認知症の情報は明らかになっていない。疾病経過や精神症状が与える疾病負担を医療、介護の面よりデルファイ法と医療経済モデルで見える化するためのシミュレーションが行われた。
2014年と2050年の人口動態を比較すると、2014年では6人の労働者が1人の高齢者を支えるのが、2050年には2人の労働者が1人の高齢者を支えることになる。
認知症疾病後の経過をシミュレーションしていくと、診断後10年にはすべての患者に重篤な症状が見られる。人口動態も含めかなり大きな問題となる。
解決策として、治療介入あり、なしでは費用推計(薬剤における)がどうなるか算出している。治療介入ありでは年間45万円で、治療介入なしでは年間48万円と3万円の差が見られた。シミュレーションとしては介入ありが望ましいと出たが、リアルワールドとしてはどうか、検証していく必要がある。
 最後は、高齢化が著しい市である長崎県五島市のリアルワールドの取組みについて。
最後は、高齢化が著しい市である長崎県五島市のリアルワールドの取組みについて。
市の高齢化率は35%に及び、10年後には44%を越え、全国的にも高い高齢化率である。現在、市には調剤共有システムが導入されている。事前にデータの2次利用を行うための同意を市民から得ている。調剤共有システムは、市内の全保険薬局が参画し、住民すべての薬歴や電子カルテ、地域包括ケアの情報が収集されている。このデータにより緊急時の対応や、クラウド型(遠隔バックアップ)のため災害時も活用ができる。
しかし、これらのデータからはQOLに関するものは取得できないため、地域包括ケアや医療情報共有の仕組みの中で、試験や調査によって取りに行かなければならいない。
QOLまで取ることでどうデータ価値を高めるか検討していくべきであろう。
セッション5
多方面から協働する重要性:新薬に付加価値を与え、安全性を保つために必要な組織構成
エグゼクティブ・パネルディスカッション:日本医薬品業界において、RWDをどのように推進すべきか
モデレーター:クライセル・ネイト氏(Astellas Pharma, Inc. リアルワールドインフォマティクス 機能長)
パネラー:
青木事成氏(中外製薬株式会社 安全性データマネジメント部 疫学グループ マネージャー)
今井博久氏(国立保健医療科学院 疫学統計研究分野 統括研究官)
岩崎宏介氏(ミリマン・インク 日本におけるヘルスケア部門およびデータ分析部門 ディレクター)
柴田敦子氏(アムジェン グローバル安全性&ラベリング部門 エグゼクティブ メディカル ディレクター)
 2日目最後に行われたパネルディスカッションでは、製薬企業、ベンダー企業、アカデミック、政府等、複数の視点でRWDをどのように推進していくべきかが議論されました。世界的にもまだ明確な指標がない中で、日本の特性をどのように活かしていくべきなのか? 特にがんや認知症に関しての取組みは日本が先行すると見られています。
2日目最後に行われたパネルディスカッションでは、製薬企業、ベンダー企業、アカデミック、政府等、複数の視点でRWDをどのように推進していくべきかが議論されました。世界的にもまだ明確な指標がない中で、日本の特性をどのように活かしていくべきなのか? 特にがんや認知症に関しての取組みは日本が先行すると見られています。
ディスカッションでは、人材育成あり方、データ共有の必要性、データ取得により何を還元するのか明確にする必要があること等が取り上げられました。
最後にモデレーターのネイト氏より、RWDの将来の展望は?日本がリーダーシップを担うために何が必要なのか?パネラーに質問しました。
<日本におけるRWDと、日本がどのようにリーダーシップを担うべきか?>
柴田氏:日本のデータは非常にリッチで使い勝手がよい。この点はアピールできる。また日本は国民介護保険がしっかりしていて、医療の流れも説明しやすく、データのクオリティも高いといえる。リサーチクエスチョンとして応用の可能性があることを伝えていくと関心が高まると思われる。
青木氏:残念ながら科学者は情報をシェアしようとしない傾向がある。それは競争があるため。それ自体は否定することではないが、こと希少疾病に関してはデータ共有できないと、1人の患者だけでは病名を特定することすらできない。希少疾病に関わる医師は綿密な情報を出していけるのが望ましい。これが文化になっていければ、糖尿病や肺がん胃がん等、莫大なデータを研究している方達にもよい影響を与えられる。それにより妥当であり、合理的なよい国だと評価されると思われる。
岩崎氏:テクニカル的な面では、個人の情報を紐付けることが重要になってくる。例えば電子お薬手帳の情報、あるいは自動販売機でジュースを買うデータ等は溢れているが、我々医学に携わる方々にとっては、これらの情報が個人に紐付けられていないと意味がない。個人情報保護とは逆行する考えかもしれないが、今後推進するエンジンになる。
今井氏:政府、アカデミア、プロバイダー、製薬企業、薬局、そして保険者(健康保険組合)もRWDのコンソーシアムに入れて活用したい。例えば保険組合での取組みとして、薬を10錠以上飲んでいる人を対象に、どのように減らすことができるか、医師にヒアリングしながら検証を行っている。この取組みで患者の健康アウトカムの改善となり、無駄な医療費削減につながる。リアルなデータの活用がこれらの貢献に繋がる。
<RWDにおいて新しいテクノロジーはどうあるべきか?>
岩崎氏:情報だけで考えると情報はあればあるほどよい。テクノロジーに期待することは情報をよく取ってくれることではないか。睡眠の状態や日々の生活いおけるストレスの状態を判断してくれる等、あればあるほどリッチな情報になってよりよいRWDになる。
柴田氏:今後、製薬企業はサービス産業化しないとならない。色々な課題はあるが、発想としては患者(カスタマー)と直接やり取りをして、すぐにオンラインでアンケートを取ってデータに活かす環境作りがRWDには求められる。

今井氏:RWDには多様性が大切になる。ビックデータを使って何をアウトカムできるかが重要になる。ベンダーと製薬企業だけの狭い中でやっていては建設的なイノベーションは生まれてこない。
青木氏:エピマクスのプロジェクトで足りなかったのは社会心理学や行動経済学等の視点だった。このような視点を持つ人材は製薬産業の中では育たない。これらのプロフェッショナルは外にいる。外の人と適切な会話ができるようになることも重要なポイントである。
パネルディスカッションから「RWDにはカスタマーの日々の情報が必要になってくる」とのコメントがありました。このデータは医療業界だけで取っていくのは難しいものとなり、外部との連携が必要になってきます。しかし、買い物のようにIDカード等が紐付いて勝手にデータが取れるものはよいですが、健康な状態における体に関するデータ(体重、活動量、血圧、食事内容等)をカスタマーに取り続けてもらうのは、とても困難であることは、過去にもGoogle Health等で実証されています。議論でもありました、何のためにデータを取るのか、自分にとって取り続ける価値があるのかを、しっかりと提示していくことが必要になるでしょう。
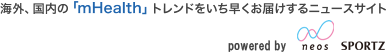



Comments are closed.