12وœˆ4ï½5و—¥مپ®2و—¥é–“م€پو¸‹è°·مƒ’م‚«مƒھم‚¨مƒ›مƒ¼مƒ«ï¼ˆو±ن؛¬ و¸‹è°·ï¼‰مپ«مپ¦م€ژHealth 2.0 Asia – Japan 2018م€ڈمپŒé–‹ه‚¬مپ•م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚
1و—¥ç›®مپ«ç¶ڑمپچ2و—¥ç›®مپ®مƒ¬مƒمƒ¼مƒˆمپ§مپ¯م€پ特مپ«و³¨ç›®مپŒé›†مپ¾مپ£مپ¦مپ„مپںمƒ”مƒƒمƒپم‚³مƒ³مƒ†م‚¹مƒˆم‚’ç´¹ن»‹مپ—مپ¾مپ™م€‚
(هڈ–وگï¼ڑو¸،è¾؛و¦هڈ‹ï¼‰

â– مƒ”مƒƒمƒپم‚³مƒ³مƒ†م‚¹مƒˆ
ه¯©وں»ه“،ï¼ڑ
هژںç”°وکژن¹…و°ڈ(مƒ•م‚،م‚¤م‚¶مƒ¼و ھه¼ڈن¼ڑ社)
هٹ 藤由ه°†و°ڈ(و±ن؛¬و€¥è،Œé›»é‰„و ھه¼ڈن¼ڑ社)
ه°ڈو—è³¢و²»و°ڈ(م‚·مƒ‹مƒ•م‚£م‚¢مƒ³و ھه¼ڈن¼ڑ社)
Georgia Mitsiو°ڈ(Sunovion Pharmaceuticals Inc.)
ه®®ç”°و‹“ه¼¥و°ڈ(م‚¹م‚¯مƒ©مƒ مƒ™مƒ³مƒپمƒ£مƒ¼م‚؛)
ه¯؛ه°¾ه¯§هگو°ڈ(مƒ¤مƒ³م‚»مƒ³مƒ•م‚،مƒ¼مƒو ھه¼ڈن¼ڑ社)
ه ¤éپ”ç”ںو°ڈ(Gree Venturesو ھه¼ڈن¼ڑ社)
و¢…و¾¤é«کوکژو°ڈ(A.T. م‚«مƒ¼مƒ‹مƒ¼ï¼‰
و¸،è¾؛و´‹ن¹‹و°ڈ(و—¥وœ¬çµŒو¸ˆو–°èپ社)
Matthew Holtو°ڈ(Health 2.0)
çں³è¦‹é™½و°ڈ(مƒ،مƒ‰مƒ”م‚¢و ھه¼ڈن¼ڑ社)
مƒ•م‚،م‚¤مƒٹمƒھم‚¹مƒˆï¼ڑ
ن¹…ن؟وپ’ه¤ھو°ڈآ (Ubieو ھه¼ڈن¼ڑ社)
وœ¨ن¸‹وکŒن¹‹و°ڈ(مƒ‡م‚¤مƒ–مƒ¬م‚¤م‚¯و ھه¼ڈن¼ڑ社)
ن¸è¥؟و™؛ن¹‹و°ڈ(و ھه¼ڈن¼ڑ社T-ICU)
ه €ç”°ن¼¸ه‹و°ڈ(و ھه¼ڈن¼ڑ社م‚¸مƒ¼م‚±م‚¢ï¼‰
ç¦ڈè°·ç›´ن؛؛و°ڈ(و ھه¼ڈن¼ڑ社مƒگمƒƒم‚¯مƒ†مƒƒم‚¯ï¼‰
ه²¸و…¶ç´€و°ڈ(HoloAsh, Inc.)
م€ژHealth 2.0 Asia – Japanم€ڈمپ«مپ¦و¯ژه¹´وپ’ن¾‹مپ¨مپھمپ£مپں<مƒ”مƒƒمƒپم‚³مƒ³مƒ†م‚¹مƒˆï¼مپ¯م€پو—¥وœ¬مپ«مپٹمپ‘م‚‹مƒکمƒ«م‚¹مƒ†مƒƒم‚¯مپ®é»ژوکژوœںمپ¨è¨€مپˆم‚‹çڈ¾هœ¨م€پ“م‚†م‚ٹمپ‹مپ”مپ‹م‚‰ه¢“ه ´مپ¾مپ§â€ن؛؛مپ®م‚ˆم‚ٹ良مپڈç”ںمپچم‚‹م‚’مƒ†مƒ¼مƒمپ«م€پمƒ†م‚¯مƒژمƒم‚¸مƒ¼مپ§مپ©مپ†ه®ںçڈ¾مپ™م‚‹مپ‹ï¼ںم€€مپ«مƒ•م‚©مƒ¼م‚«م‚¹م‚’ه½“مپ¦مپ¦م€پمپمپ®م‚ˆمپ†مپھم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’ن½œم‚‹مƒپمƒ¼مƒ م‚’ه؟œوڈ´مپ™م‚‹ç›®çڑ„مپ§é–‹ه‚¬مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
ن»ٹه›مپ¯60و•°ç¤¾مپ®ه؟œه‹ںمپ®ن¸مپ‹م‚‰م€پمƒ•م‚،م‚¤مƒٹمƒھم‚¹مƒˆمپ¨مپ—مپ¦6社مپŒéپ¸مپ°م‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚وœ€ه„ھ秀è³ï¼ˆ1社)مپ«مپ¯م€پè³é‡‘100ن¸‡ه††مپ¨و¥ه¹´9وœˆمپ«ç±³ه›½مپ§é–‹ه‚¬مپ•م‚Œم‚‹م€ŒHealth 2.0 Annual Fall Conferenceم€چمپ®مƒڑم‚¢مƒپم‚±مƒƒمƒˆمپŒوڈگن¾›مپ•م‚Œمپ¾مپ™م€‚
م‚³مƒ³مƒ†م‚¹مƒˆمپ¯م€پمƒ•م‚،م‚¤مƒٹمƒھم‚¹مƒˆهگ„社مپŒ5هˆ†مƒ—مƒ¬م‚¼مƒ³م€په¯©وں»ه“،مپŒ10هˆ†è³ھه•ڈمپ™م‚‹وµپم‚Œمپ§è،Œم‚ڈم‚Œمپ¾مپ—مپںم€‚ن»ٹه›مپ¯6社مپ®مƒ—مƒ¬م‚¼مƒ³ه†…ه®¹م‚’مƒ¬مƒمƒ¼مƒˆمپ—مپ¾مپ™م€‚
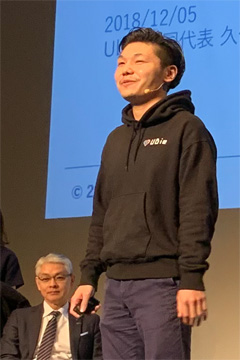 AIه•ڈè¨؛Ubieï¼ڈن¹…ن؟وپ’ه¤ھو°ڈ
AIه•ڈè¨؛Ubieï¼ڈن¹…ن؟وپ’ه¤ھو°ڈ
و‚£è€…مپ®ه¾…مپ،و™‚é–“مپ«م€پهŒ»ه¸«مپ¯é›»هگم‚«مƒ«مƒ†مپ®ه…¥هٹ›م‚’è،Œمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚هŒ»ه¸«مپ«مپ¨مپ£مپ¦مپ¯ه¤§مپچمپھè² و‹…مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ه¤–و¥1و™‚é–“مپ«ه¯¾مپ—م€پمƒ‡م‚¹م‚¯مƒ¯مƒ¼م‚¯مپŒ2و™‚é–“مپ«ç›¸ه½“مپ™م‚‹م€‚
ن»¥ه‰چمپ¯ç´™مپ®ه•ڈè¨؛票مپŒن½؟م‚ڈم‚Œمپ¦مپ„مپںمپŒم€پç´™مپ®ه•ڈè¨؛票مپ«مپ¯هŒ»ç™‚وƒ…ه ±مپŒه°‘مپھمپ„مپںم‚پم€په®ںéڑ›مپ«مپ¯مپ‚مپ¾م‚ٹèھمپ¾م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ‹مپ£مپںم€‚مپم‚Œم‚‰مپ®ه•ڈé،Œم‚’م€ژAIه•ڈè¨؛Ubieم€ڈمپ§è§£و±؛مپ™م‚‹م€‚
م€ژAIه•ڈè¨؛Ubieم€ڈم‚’ن½؟مپ†مپ¨م€پمپ¾مپڑو‚£è€…مپŒه•ڈè¨؛مپ«ه›ç”م‚’مپ™م‚‹م€‚مپم‚Œم‚’ه…ƒمپ«هŒ»ه¸«مپŒè¨؛ه¯ںمپ®ه‰چمپ«ç¢؛èھچمپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹م€‚مپمپ®ه†…ه®¹م‚’é›»هگم‚«مƒ«مƒ†مپ«م‚³مƒ”مƒ¼مپ§مپچم‚‹م€‚مپ“م‚Œمپ«م‚ˆم‚ٹه…¥هٹ›ن½œو¥مپŒه¤§ه¹…مپ«ه‰ٹو¸›مپ§مپچم‚‹م€‚
م€ژAIه•ڈè¨؛Ubieم€ڈمپ®ç‰¹ه¾´مپ¯م€پè³ھه•ڈم‚’AIمپŒéپ¸مپ¶مپ¨مپ“م‚چم€‚ç´™مپ§مپ¯مپ§مپچمپھمپ„و‚£è€…مپ®ç—‡çٹ¶مپ«éپ©مپ—مپںه•ڈè¨؛مپŒهڈ¯èƒ½مپ«مپھم‚‹م€‚
مپ¾مپںهŒ»ه¸«مپŒم€ژAIه•ڈè¨؛Ubieم€ڈم‚’ن½؟مپ£مپ¦م€پو‚£è€…مپ®çٹ¶و…‹م‚’è¨؛مپ¦مپ‹م‚‰ç—…هگچم‚’مپ¤مپ‘م‚‹مƒ—مƒم‚»م‚¹مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚
م€ژAIه•ڈè¨؛Ubieم€ڈه°ژه…¥مپ«م‚ˆم‚ٹم€په¤–و¥مپ®ه•ڈè¨؛و™‚é–“مپ¯ن»¥ه‰چمپ®1/3مپ«مپھمپ£مپںم€‚مپ™مپ§مپ«50ن»¥ن¸ٹمپ®ç—…院م‚„م‚¯مƒھمƒ‹مƒƒم‚¯مپ«ه°ژه…¥مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚
مپمپ®ن»–م€پو‚£è€…هگ‘مپ‘م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚‚و¤œè¨ژمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚çڈ¾هœ¨م€ŒDr.Ubieم€چم‚¢مƒ—مƒھم‚’Google Playم‚¹مƒˆم‚¢مپ«وڈگن¾›مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ç—‡çٹ¶م‚’ه…¥هٹ›مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§ç—…و°—مپŒن؛ˆو¸¬مپ§مپچم€پ病院مپ«è،Œمپڈمپ¹مپچمپ‹م€په¯¾ه‡¦ç™‚و³•مپ§م‚ˆمپ„مپ‹م‚’çں¥م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹م€‚çڈ¾هœ¨م‚¤مƒ³مƒ‰مپ§م‚‚وڈگن¾›م‚’مپ¯مپکم‚پمپںم€‚
و‚£è€…مپ®çٹ¶و³پمپ«هگˆم‚ڈمپ›م€پéپ©هˆ‡مپھهŒ»ç™‚م‚’هڈ—مپ‘مپ¦م‚‚م‚‰مپˆم‚‹م‚ˆمپ†è²¢çŒ®مپ—مپ¦مپ„مپچمپںمپ„م€‚
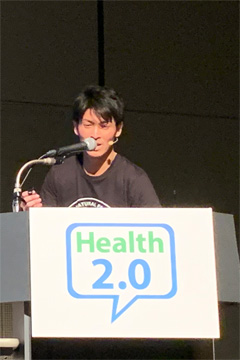 HENOHENOï¼ڈوœ¨ن¸‹وکŒن¹‹و°ڈ
HENOHENOï¼ڈوœ¨ن¸‹وکŒن¹‹و°ڈ
مƒ•مƒ¼مƒ‰مƒم‚¹م‚’ه†·ه‡چمپ§è§£و±؛مپ™م‚‹مƒ‡م‚¤مƒ–مƒ¬م‚¤م‚¯مپ¯م€پ特و®ٹه†·ه‡چم‚’è،Œمپ†é£ںه“په†·ه‡چوٹ€è،“م‚’وڈگن¾›مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚特و®ٹه†·ه‡چمپ¯é€ڑه¸¸م‚ˆم‚ٹه†·ه‡چمپŒو—©مپ„مپںم‚پم€پ解ه‡چمپ®ه†چçڈ¾و€§مپŒé«کمپ„م€‚
مƒ‡م‚¤مƒ–مƒ¬م‚¤م‚¯مپ¯2مپ¤مپ®ç¤¾ن¼ڑèھ²é،Œمپ«هڈ–م‚ٹ組م‚“مپ§مپ„م‚‹م€‚
1مپ¤مپ¯مƒ•مƒ¼مƒ‰مƒم‚¹م€‚çڈ¾هœ¨و—¥وœ¬مپ§مپ¯ه¹´é–“600ن¸‡مƒˆمƒ³م‚‚مپ®é£ںه“پمپŒç ´و£„مپ•م‚Œم€پ焼هچ´مپ«1,200ه„„ه††م‚‚مپ‹مپ‹مپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ه»ƒو£„مپ®çژ‡مپŒé«کمپ„مپ®مپ¯é‡ژèڈœمپ¨وœç‰©م€‚مپ¾مپڑمپ¯ه¸‚ه ´مپ‹م‚‰ه‡؛م‚‹مƒم‚¹م‚’解و±؛مپ™م‚‹م€‚
م‚‚مپ†1مپ¤مپ¯وœھç—…م€‚هپ¥ه؛·ه¯؟ه‘½م‚’ن¼¸مپ°مپ™مپںم‚پمپ®هڈ–م‚ٹ組مپ؟م‚’é£ںن؛‹مپ§è€ƒمپˆمپںم€‚مپŒم‚“م‚„ç³–ه°؟ç—…م‚’و¸›ه°‘مپ•مپ›م‚‹é£ں物ç¹ٹç¶م‚’ه¤ڑمپڈهگ«مپ؟م€پè€پهŒ–ç´°èƒمپ®ه¢—هٹ م‚’éک²مپگمƒ•م‚£م‚»مƒپمƒ³م‚‚ه¤ڑمپڈهگ«م‚€م€پمƒ‰مƒ¼مƒ‘مƒںمƒ³مپŒه‡؛م‚‹م‚ˆمپ†مپ«و¥½مپ—مپ„é£ںن؛‹مپŒمپ§مپچم‚‹مپںم‚پمپ«مƒ•مƒ«مƒ¼مƒ„مپ«ç€ç›®مپ—مپںم€‚
مپم‚Œم‚‰2مپ¤مپ®èھ²é،Œم‚’ه†·ه‡چوٹ€è،“مپ§è§£و±؛مپ™م‚‹مپ®مپŒم€پم‚‚مپ£مپںمپ„مپھمپ„م‚’مپھمپڈمپ—مپ¦م‚¦م‚§مƒ«مƒچم‚¹مپ«ه¤‰مپˆم‚‹م€پمƒ•مƒمƒ¼م‚؛مƒ³مƒ•مƒ«مƒ¼مƒ„م€ژHENOHENOم€ڈمپ§مپ‚م‚‹م€‚
وœç‰©مپ®1و—¥مپ®و‘‚هڈ–é‡ڈمپ¯200gه؟…è¦پمپ مپŒم€پ特مپ«م‚ھمƒ•م‚£م‚¹مƒ¯مƒ¼م‚«مƒ¼ï¼ˆ20ï½40ن»£ï¼‰مپŒن¸چ足مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚و‰‹è»½مپ«é£ںمپ¹مپ¦م‚‚م‚‰مپ†مپںم‚پم€پن¼پو¥مپ®م‚ھمƒ•م‚£م‚¹مپ«مƒ‡م‚¶مƒ¼مƒˆمپ¨مپ—مپ¦م€ژHENOHENOم€ڈمپ®وڈگن¾›م‚’مپ¯مپکم‚پمپںم€‚
مƒ“م‚¸مƒچم‚¹مƒ¢مƒ‡مƒ«مپ¯م€په¸‚ه ´مپ‹م‚‰ç ´و£„مپ•م‚Œم‚‹وœç‰©م‚’ه¼•مپچهڈ–م‚ٹم€پمƒ‡م‚¤مƒ–مƒ¬م‚¤م‚¯مپ§هٹ ه·¥مپ—م‚ھمƒ•م‚£م‚¹مپ«ه±ٹمپ‘م‚‹م€‚
هپ¥ه؛·çµŒه–¶م‚’وژ¨ه¥¨مپ™م‚‹ن¼پو¥مپŒن¸ه؟ƒمپ«è³¼ه…¥ï¼ˆه¾“و¥ه“،مپŒن¸€éƒ¨è² و‹…)مپ—م€په¾“و¥ه“،مپ«وڈگن¾›مپ™م‚‹م€‚
مپ“مپ®هڈژç›ٹمپ®ن¸€éƒ¨م‚’ه¸‚ه ´م‚„ç”ں産者مپ«é‚„ه…ƒمپ™م‚‹م€‚
م€ژHENOHENOم€ڈمپ¯ه›½ç”£م€پç„،و·»هٹ مپ§ه®‰ه؟ƒم€‚ه†·ه‡چوٹ€è،“مپ§ç”ںم‚ˆم‚ٹم‚‚و „é¤ٹمپŒن؟مپںم‚Œم‚‹م€‚ه¾“و¥ه“،مپ¯ç½ھو‚ھو„ںمپ®مپھمپ„مپٹم‚„مپ¤مپ¨مپ—مپ¦é£ںمپ¹م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹م€‚
 T-ICUï¼ڈن¸è¥؟و™؛ن¹‹و°ڈ
T-ICUï¼ڈن¸è¥؟و™؛ن¹‹و°ڈ
çڈ¾هœ¨م€پ集ن¸و²»ç™‚ه®¤ï¼ˆن»¥ن¸‹ICU)ه°‚é–€هŒ»مپŒن¸چ足مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚و—¥وœ¬مپ§ICUه°‚é–€هŒ»مپ¯هŒ»ه¸«ه…¨ن½“مپ®0.5%(1,600ن؛؛)مپ—مپ‹مپٹم‚‰مپڑم€پمپمپ®ه°‚é–€هŒ»م‚‚ه¤§و‰‹ç—…院مپھمپ©300箇و‰€مپ«é›†ن¸مپ™م‚‹مپںم‚پم€پ800箇و‰€مپ§ه°‚é–€هŒ»مپŒمپ„مپھمپ„çٹ¶و…‹مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ICUمپ«ه…¥é™¢مپ—مپ¦م‚‚70%مپ®ç¢؛çژ‡مپ§ه°‚é–€هŒ»مپ«è¨؛مپ¦م‚‚م‚‰مپ†مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپھمپ„مپ¨è¨€م‚ڈم‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚
م€ژT-ICUم€ڈمپ¯م€په°‚é–€هŒ»مپŒéپ éڑ”مپ§م€په°‚é–€هŒ»مپŒمپ„مپھمپ„ICUمپ«مپ„م‚‹هŒ»ه¸«م‚’م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپ™م‚‹م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ§مپ‚م‚‹م€‚
ه°‚é–€هŒ»مپŒم‚µمƒمƒ¼مƒˆم‚»مƒ³م‚؟مƒ¼مپ«24و™‚é–“ه¾…و©ںمپ—م€پ病院مپ‹م‚‰è¨؛療مپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ®ç›¸è«‡م‚’هڈ—مپ‘م‚‹مپ¨م€په؟ƒé›»ه›³مƒ¢مƒ‹م‚؟مƒ¼م€پCTم€پMRIمپ®ç”»هƒڈم‚’éپ éڑ”مپ§ه…±وœ‰مپ—مپھمپŒم‚‰م‚¢مƒ‰مƒگم‚¤م‚¹م‚’è،Œمپ†م€‚
ç±³ه›½مپ§مپ¯م€پمپ“مپ®م‚ˆمپ†مپھم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپŒ20ه¹´ه‰چمپ‹م‚‰ه§‹مپ¾مپ£مپ¦مپٹم‚ٹم€پ1ن؛؛مپ®ه°‚é–€هŒ»مپŒ30箇و‰€مپ®ICUم‚’م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚
ه›½ه†…مپ§مپ¯2ه¹´ه‰چمپ‹م‚‰ه§‹م‚پمپںم€ژT-ICUم€ڈمپ®مپ؟مپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚ن»ٹه¾Œم€په›½ه†…160病院مپ®م‚µمƒمƒ¼مƒˆم‚’مپ—مپ¦م€په¹´é–“16ه„„ه††مپ®هڈژç›ٹم‚’ç›®وŒ‡مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚
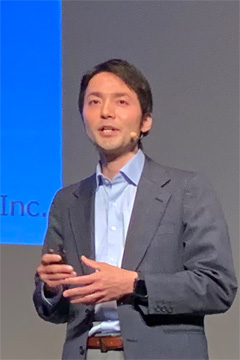 ç‚ژç—‡و€§è…¸ç–¾و‚£و‚£è€…éپ éڑ”مƒ¢مƒ‹م‚؟مƒھمƒ³م‚°ï¼ڈه €ç”°ن¼¸ه‹و°ڈ
ç‚ژç—‡و€§è…¸ç–¾و‚£و‚£è€…éپ éڑ”مƒ¢مƒ‹م‚؟مƒھمƒ³م‚°ï¼ڈه €ç”°ن¼¸ه‹و°ڈ
م‚¸مƒ¼م‚±م‚¢مپ¯èھ°م‚‚مپŒه؟…è¦پمپھمپ¨مپچمپ«ه؟…è¦پمپھهŒ»ç™‚م‚’هڈ—مپ‘م‚‰م‚Œم‚‹مپ“مپ¨م‚’ç›®çڑ„مپ«م€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒکمƒ«م‚¹مپ§و”¯وڈ´مپ™م‚‹م€‚
çڈ¾هœ¨م€پمƒ¢مƒگم‚¤مƒ«و²»ç™‚م‚¢مƒ—مƒھمپ¨م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³و”¯وڈ´مپ«هڈ–م‚ٹ組م‚“مپ§مپ„م‚‹م€‚
م‚؟مƒ¼م‚²مƒƒمƒˆمپ¨مپھم‚‹مپ®مپ¯ç‚ژç—‡و€§è…¸ç–¾و‚£م€‚ه›½ه†…22ن¸‡ن؛؛مپ®و‚£è€…مپŒمپ„مپ¦م€په¹´م€…ه¢—هٹ مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚و—¥م€…مپ®ç”ںو´»مپ«م‚‚و”¯éڑœم‚’مپچمپںمپ™مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚ٹم€پو‚£è€…مپ®ن¸مپ«مپ¯1و—¥4و™‚é–“م‚‚مƒˆم‚¤مƒ¬مپ§éپژمپ”مپ™ن؛؛م‚‚مپ„م‚‹م€‚
ç‚ژç—‡و€§è…¸ç–¾و‚£و‚£è€…مپ®مƒ‹مƒ¼م‚؛مپ¯3مپ¤م€‚1مپ¤مپ¯ç—…çٹ¶و‚ھهŒ–مپ¸مپ®وپگم‚Œم€‚2مپ¤ç›®مپ¯هڈ—è¨؛مپ¸مپ®مƒڈمƒ¼مƒ‰مƒ«م€‚ن»•ن؛‹ن¸مپھمپ©وˆ‘و…¢مپ—مپ¦و‚ھهŒ–مپ—مپ¦مپ—مپ¾مپ†مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚‹م€‚3مپ¤ç›®مپŒن»–مپ®و‚£è€…مپ¨مپ¤مپھمپŒم‚ٹن؟،é ¼و€§مپ‚م‚‹وƒ…ه ±م‚’ه¾—مپںمپ„م€پمپ¨مپ®وƒ³مپ„م€‚
3مپ¤مپ®مƒ‹مƒ¼م‚؛مپ«ه¯¾مپ—م€پ2مپ¤مپ®م‚½مƒھمƒ¥مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³م‚’وڈگن¾›مپ™م‚‹م€‚
1مپ¤مپŒم‚¢مƒ—مƒھمپ«م‚ˆم‚‹éپ éڑ”مƒ¢مƒ‹م‚؟مƒھمƒ³م‚°م€‚و‚£è€…مپ«ه°‚用م‚¢مƒ—مƒھم‚’وڈگن¾›مپ™م‚‹م€‚و‚£è€…مپ¯مپمپ®م‚¢مƒ—مƒھمپ«و—¥م€…مپ®ç—‡çٹ¶م‚’ه…¥هٹ›مپ™م‚‹م€‚م‚¸مƒ¼م‚±م‚¢مپ«وƒ…ه ±مپŒه±ٹمپڈمپ¨é‡چç—‡ه؛¦مپ®è©•ن¾،م‚’è،Œمپ†م€‚é‡چç—‡ه؛¦مپ«ه؟œمپکمپ¦مƒھم‚¢مƒ«م‚؟م‚¤مƒ ن»‹ه…¥م‚’è،Œمپ†م€‚و—©م‚پمپ«ن»‹ه…¥مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پوˆ‘و…¢مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ«م‚ˆم‚‹ç·ٹو€¥ه…¥é™¢çژ‡م‚’ن¸‹مپ’م‚‹م€‚
çڈ¾هœ¨م€پè–¬ن؛‹و‰؟èھچم€پن؟é™؛éپ©ç”¨م‚’ç›®وŒ‡مپ—مپ¦è‡¨ه؛ٹ試験م‚’è،Œمپ£مپ¦مپ„مپڈم€‚
م‚‚مپ†1مپ¤مپŒم€پç–¾و‚£هگ‘مپ‘مپ®م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³و‚£è€…م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹مƒ†م‚£م€‚هŒ»ç™‚者مپ‹م‚‰مپ®وƒ…ه ±وڈگن¾›م‚’مپ¯مپکم‚پم€پو‚£è€…م‚’ç·ڈهگˆçڑ„مپ«م‚µمƒمƒ¼مƒˆمپ—مپ¦مپ„مپڈم€‚çڈ¾هœ¨مپ¯15هگچمپ§2週間مپ®مƒ†م‚¹مƒˆم‚’è،Œمپ£مپںم€‚مپ“مپ®م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹مƒ†م‚£مپ¯م€پن؟é™؛éپ©ç”¨ه¤–مپ®م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ¨مپ—مپ¦وڈگن¾›مپ—مپ¦مپ„مپڈم€‚
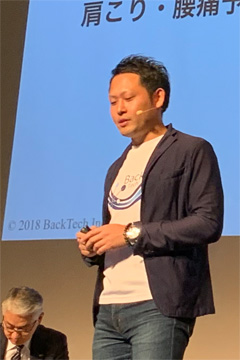 مƒم‚±مƒƒمƒˆم‚»مƒ©مƒ”م‚¹مƒˆï¼ڈç¦ڈè°·ç›´ن؛؛و°ڈ
مƒم‚±مƒƒمƒˆم‚»مƒ©مƒ”م‚¹مƒˆï¼ڈç¦ڈè°·ç›´ن؛؛و°ڈ
ه®ںمپ¯4ن؛؛مپ«1ن؛؛مپŒن½“مپ®ç—›مپ؟مپ§ن¼ڑ社م‚’ن¼‘م‚“مپ§مپ„م‚‹م€‚مپ‚م‚‹ن¼ڑ社مپ§م‚¢مƒ³م‚±مƒ¼مƒˆم‚’هڈ–مپ£مپںم‚‰م€پè‚©م‚„首م€پè…°مپ®ç—›مپ؟م‚’و„ںمپکمپ¦مپ„م‚‹ن؛؛مپŒ7ه‰²م‚‚مپ„مپںم€‚هƒچمپ„مپ¦مپ„مپ¦é›†ن¸مپ§مپچمپھمپ„çگ†ç”±مپ®1ن½چمپ«è‚©مپ“م‚ٹم€پ3ن½چمپ«è…°ç—›مپŒوŒ™مپ’م‚‰م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚è‚©مپ“م‚ٹè…°ç—›مپ¯ه¤§مپچمپھèھ²é،Œمپ م€‚
مƒگمƒƒم‚¯مƒ†مƒƒم‚¯مپ§مپ¯م€پو³•ن؛؛هگ‘مپ‘مپ«è‚©مپ“م‚ٹè…°ç—›ه¯¾ç–م‚¢مƒ—مƒھم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م€ژمƒم‚±مƒƒمƒˆم‚»مƒ©مƒ”م‚¹مƒˆم€ڈم‚’وڈگن¾›مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚
م€ژمƒم‚±مƒƒمƒˆم‚»مƒ©مƒ”م‚¹مƒˆم€ڈمپ¯éپ éڑ”مپ«م‚ˆم‚ٹم€پو‹…ه½“م‚»مƒ©مƒ”م‚¹مƒˆمپŒèھچçں¥è،Œه‹•ç™‚و³•م‚’è،Œمپ†م€‚
è‚©مپ“م‚ٹè…°ç—›مپ¯مƒ،مƒ³م‚؟مƒ«مپ§ç—›مپ؟مپŒه‡؛م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ§م€پمپمپ®ç‚¹م‚‚ه•ڈè¨؛مپ§مƒپم‚§مƒƒم‚¯مپ—مپ¦مپ„مپڈم€‚و—¥م€…مپ®è،Œه‹•مپ¯Fitbitمپ¨é€£وگ؛مپ—م€پç،çœ م‚„م‚¢م‚¯مƒ†م‚£مƒ“مƒ†م‚£مƒ‡مƒ¼م‚؟م‚’هڈ–م‚ٹم€پم‚»مƒ©مƒ”م‚¹مƒˆمپŒç¢؛èھچمپ—مپ¦مپ„مپڈم€‚
م‚³مƒ¼مƒ”مƒ³م‚°م‚¹م‚مƒ«م‚’وڈگن¾›مپ™م‚‹مپ®مپ§م€پمپمپ®ن؛؛مپ«مپ‚مپ£مپںه¯¾ه‡¦و³•م‚’見مپ¤مپ‘مپ¦مپ„مپڈمپ“مپ¨مپŒمپ§مپچم‚‹م€‚
هٹ¹وœم‚„مپمپ®مپ¨مپچمپ®و„ںوƒ…م‚’è‡ھه·±è©•ن¾،مپ—مپ¦م‚‚م‚‰مپ„م€پمپ©مپ®م‚ˆمپ†مپھمپ¨مپچمپ«ç—›مپ؟مپŒه‡؛م‚„مپ™مپ„مپ‹مپھمپ©هڈ¯è¦–هŒ–مپ—مپ¦مپ„مپڈم€‚
مƒ¦مƒ¼م‚¶مƒ¼مپ¸مپ®وƒ…ه ±وڈگن¾›مپ¯وœ€و–°مپ®è«–و–‡م‚’وœˆ50ï½100وœ¬م‚’مƒپم‚§مƒƒم‚¯مپ—م€پéپ©هˆ‡مپھوƒ…ه ±م‚’ه¼•ç”¨مپ—مپ¦وڈگن¾›مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚
م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹وڈگن¾›مپ‹م‚‰1ه¹´ن»¥ن¸ٹمپŒçµŒمپ،م€پ相談ن»¶و•°مپ¯مپ™مپ§مپ«3ن¸‡ن»¶م‚’çھپç ´مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚
م€ژمƒم‚±مƒƒمƒˆم‚»مƒ©مƒ”م‚¹مƒˆم€ڈمپ¯هپ¥ه؛·çµŒه–¶م‚’وژ¨é€²مپ—مپ¦مپ„م‚‹ن¼پو¥مپ«وڈگن¾›مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ®مپ§م€پç”ں産و€§هٹ¹وœم‚’è©•ن¾،مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚
ADHDم‚»مƒ©مƒ”مƒ¼AIï¼ڈه²¸و…¶ç´€و°ڈ
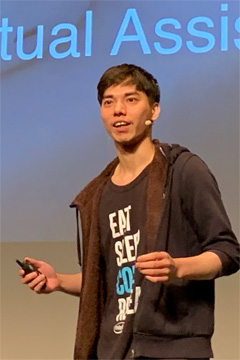 çڈ¾هœ¨م‚¹مƒمƒ¼مƒˆمƒ•م‚©مƒ³مپ«م‚ˆم‚ٹADHDç™؛ç—‡مپŒه¢—هٹ مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ç±³ه›½مپ§مپ¯2,000ن¸‡ن؛؛مپŒè¨؛و–مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپŒم€پè¨؛و–مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ„ه±¤م‚‚هگŒمپکمپڈ2,000ن¸‡ن؛؛程ه؛¦مپŒوƒ³ه®ڑمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚
çڈ¾هœ¨م‚¹مƒمƒ¼مƒˆمƒ•م‚©مƒ³مپ«م‚ˆم‚ٹADHDç™؛ç—‡مپŒه¢—هٹ مپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ç±³ه›½مپ§مپ¯2,000ن¸‡ن؛؛مپŒè¨؛و–مپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹مپŒم€پè¨؛و–مپ•م‚Œمپ¦مپ„مپھمپ„ه±¤م‚‚هگŒمپکمپڈ2,000ن¸‡ن؛؛程ه؛¦مپŒوƒ³ه®ڑمپ•م‚Œمپ¦مپ„م‚‹م€‚
ç±³ه›½مپ§ADHDو‚£è€…مپ«مƒ’م‚¢مƒھمƒ³م‚°مپ—مپںمپ¨مپ“م‚چم€پو²»ç™‚مپ«و¯ژوœˆ15,000ه††ç¨‹ه؛¦ن½؟مپ£مپ¦مپ„مپںم€‚مپںمپ مپ—م‚»مƒ©مƒ”مƒ¼مپ¯هڈ—مپ‘مپںمپ„م‚؟م‚¤مƒںمƒ³م‚°مپ§ن؛ˆç´„مپŒمپ§مپچمپھمپ‹مپ£مپںم‚ٹم€پè–¬مپ¯ه‰¯ن½œç”¨مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ§ه¸¸و™‚飲م‚€مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپھمپ„م€‚
مپمپ“مپ§م€پ24و™‚é–“م‚¢م‚¯م‚»م‚¹مپ§مپچمپ¦é‡‘é،چم‚‚ه®‰مپڈم€په‰¯ن½œç”¨م‚‚مپھمپ„م‚½مƒھمƒ¥مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³مپ¨مپ—مپ¦م€پAIمپ«م‚ˆم‚‹م‚»مƒ©مƒ”مƒ¼م‚’é–‹ç™؛مپ—مپںم€‚
AIمپ«م‚ˆم‚‹م‚»مƒ©مƒ”مƒ¼مپ¨مپ—مپ¦م€پمƒ¢مƒپمƒ™مƒ¼م‚·مƒ§مƒٹمƒ«م‚¤مƒ³م‚؟مƒ“مƒ¥مƒ¼م‚’è،Œمپ†م€‚
مƒ—مƒھمƒ³م‚·مƒ‘مƒ«مپ¨مپ—مپ¦م€Œه…±و„ںم€پم‚®مƒ£مƒƒمƒ—مپ®çگ†è§£م€پè°è«–م‚’مپ•مپ›م€پè‡ھه·±هٹ¹هٹ›و„ںم‚’ن¸ٹمپ’م‚‹م€چمپ®4مپ¤مپŒمپ‚م‚‹م€‚
مƒ‡مƒ¼م‚؟مپ¯مپ™مپ§مپ«1ن¸‡ن»¶مپ»مپ©è“„ç©چمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚ç±³ه›½مپ§م‚³مƒ³م‚·مƒ¥مƒ¼مƒهگ‘مپ‘م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ¨مپ—مپ¦وڈگن¾›مپ™م‚‹م€‚ن¾،و ¼مپ¯وœˆ1,500ه††ç¨‹ه؛¦مپ§و¯ژو—¥م‚»مƒ©مƒ”مƒ¼مپŒ24و™‚é–“هڈ—مپ‘م‚‰م‚Œم‚‹م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپ¨مپ—مپ¦وڈگن¾›مپ™م‚‹ن؛ˆه®ڑم€‚
م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³مپ¯م‚¢مƒ—مƒھمپ®ن»–م€پAmazon alexa(م‚¹مƒمƒ¼مƒˆم‚¹مƒ”مƒ¼م‚«مƒ¼ï¼‰م‚’هˆ©ç”¨مپ—مپ¦وڈگن¾›مپ—مپ¦مپ„مپڈم€‚
ه°†و¥çڑ„مپ«مپ¯ç‹¬è‡ھمپ®مƒڈمƒ¼مƒ‰م‚¦م‚§م‚¢م‚’é–‹ç™؛مپ—م€پم‚ھمƒ¼مƒ‡م‚£م‚ھمپ مپ‘مپ§مپھمپڈمƒ“م‚¸مƒ¥م‚¢مƒ«م‚‚وڈگن¾›مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپ§م€پو³¨و„ڈو•£و¼«مپ«مپھم‚ٹم‚„مپ™مپ„ADHDو‚£è€…مپŒم€پم‚ˆم‚ٹ集ن¸مپ—م‚„مپ™مپ„ç’°ه¢ƒم‚’وڈگن¾›مپ—مپ¦مپ„مپڈم€‚
 6社ه…±مپ«èˆˆه‘³و·±مپ„ه†…ه®¹مپ§م€پمپ©م‚Œم‚‚社ن¼ڑçڑ„و„ڈ義مپ®é«کمپ„م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپŒوڈگن¾›مپ•م‚Œم‚‹مپ¨و„ںمپکمپ¾مپ—مپںم€‚
6社ه…±مپ«èˆˆه‘³و·±مپ„ه†…ه®¹مپ§م€پمپ©م‚Œم‚‚社ن¼ڑçڑ„و„ڈ義مپ®é«کمپ„م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹مپŒوڈگن¾›مپ•م‚Œم‚‹مپ¨و„ںمپکمپ¾مپ—مپںم€‚
ه½“و—¥è،Œم‚ڈم‚Œمپںه„ھ秀è³ç™؛è،¨مپ§مپ¯م€پè‚©مپ“م‚ٹè…°ç—›ه¯¾ç–م‚¢مƒ—مƒھم‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م€ژمƒم‚±مƒƒمƒˆم‚»مƒ©مƒ”م‚¹مƒˆم€ڈم‚’وڈگن¾›مپ™م‚‹مƒگمƒƒم‚¯مƒ†مƒƒم‚¯ç¤¾مپ®ç¦ڈè°·و°ڈمپŒهڈ—è³مپ—مپ¾مپ—مپںم€‚
ç¦ڈè°·و°ڈمپ¸مپ¯م€په¾Œو—¥هچک独م‚¤مƒ³م‚؟مƒ“مƒ¥مƒ¼م‚’è،Œمپ„مپ¾مپ—مپںم€‚مپ“مپ،م‚‰م‚‚مپ”覧مپڈمپ مپ•مپ„م€‚
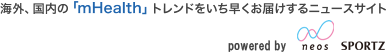



Comments are closed.