 гАОmHealth WatchгАПгБІгБѓгАБгБУгБУжЬАињСгБІеЕђйЦЛгБХгВМгБЯгГЛгГ•гГЉгВєгБЛгВЙгАМж≥®зЫЃгГЛгГ•гГЉгВєгАНгВТгГФгГГгВѓгВҐгГГгГЧгБЧгАБзЛђиЗ™гБЃи¶ЦзВєгБІиІ£и™ђгБЧгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ
гАОmHealth WatchгАПгБІгБѓгАБгБУгБУжЬАињСгБІеЕђйЦЛгБХгВМгБЯгГЛгГ•гГЉгВєгБЛгВЙгАМж≥®зЫЃгГЛгГ•гГЉгВєгАНгВТгГФгГГгВѓгВҐгГГгГЧгБЧгАБзЛђиЗ™гБЃи¶ЦзВєгБІиІ£и™ђгБЧгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ
дїКеЫЮж≥®зЫЃгБЧгБЯгГЛгГ•гГЉгВєгБѓгБУгБ°гВЙпЉБ
пЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭ
вАЬжВ£иАЕгБЂеКЫгВТдЄОгБИгВЛ3гБ§гБЃmHealthжКАи°У – гБЭгБЧгБ¶еМїиАЕвАЭ
дїКеєігБЂгБ™гБ£гБ¶гАБжКАи°Уз≥їе§ІжЙЛ3е§ІдЉБж•≠гБѓгБЭгБЃи£љеУБгГ©гВ§гГ≥гВТжЛ°е§ІгБЧгАБгГЗгВЄгВњгГЂеМїзЩВгБЂеѓЊењЬгБЧгБ¶гБДгВЛгАВгБХгВЙгБЂGlobal Mobile Health Market ReportгБЂгВИгВЛгБ®гАБгГҐгГРгВ§гГЂгГШгГЂгВєеЄВе†ігБѓ2017еєігБЊгБІгБЂеЕ®дЄЦзХМзЪДгБЂ260еДДгГЙгГЂгБЂйБФгБЩгВЛгБ®дЇИжЄђгБЧгБ¶гБДгВЛгАВгГШгГЂгВєгВ±гВҐжКАи°УгБѓгАБжґИи≤їиАЕеЄВе†ігВТжФѓйЕНгБЧгБ§гБ§гБВгВЛгБ†гБСгБІгБ™гБПгАБзЧЕйЩҐгВДи®ЇзЩВжЙАгБЂжА•йАЯгБЂе∞ОеЕ•гБХгВМгБ¶гБДгВЛгАВeHealth Standards and Servicesз§ЊгБЃCMSпЉИгВ≥гГ≥гГЖгГ≥гГДгГЮгГНгВЄгГ°гГ≥гГИгВЈгВєгГЖгГ†пЉЙйГ®йЦАгБІгАБжФњз≠ЦеПКгБ≥жЩЃеПКжіїеЛХгБЃеЕИе∞ОгВТеЛЩгВБгВЛElisabeth Myersж∞ПгБЃе†±еСКгБЂгВИгВЛгБ®гАБ2014еєі5жЬИзПЊеЬ®гАБзЧЕйЩҐгВДеМїеЄЂгБЯгБ°гБѓйЫїе≠РеМїзЩВи®ШйМ≤гБЃе•®еʱ冱йЕђгБ®гБЧгБ¶237еДДгГЙгГЂгБМжФѓжЙХгВПгВМгБ¶гБДгВЛгБ®гБДгБЖгАВи®ЇзЩВжЙАгБЂгБКгБСгВЛгГШгГЂгВєгВ±гВҐITпЉИдї•дЄЛHITпЉЙгБЃе∞ОеЕ•гБЂгВИгВКгАБжВ£иАЕгБЃгГШгГЂгВєгВ±гВҐгБМз∞°дЊњгБЂгБ™гБ£гБ¶гБНгБ¶гБДгВЛгАВгБЭгБЃзРЖзФ±гБѓгАБHITгБЂгВИгБ£гБ¶жВ£иАЕгБМиЗ™еИЖиЗ™иЇЂгБІеБ•еЇЈзЃ°зРЖгБІгБНгВЛгБЯгВБгБ†гАВ
гБІгБѓеМїеЄЂгБ®гБЧгБ¶гБѓгАБгБ©гБЖгБЩгВМгБ∞иЗ™еИЖгБЃжВ£иАЕгБМеЄЄгБЂеБ•еЇЈзЃ°зРЖгБЂеПЦгВКзµДгБњгАБгБЛгБ§гБЭгВМгБМеЃЯи°МеПѓиГљгБ™зКґжЕЛгВТзґЩзґЪгБХгБЫгВЙгВМгВЛгБЃгБ†гВНгБЖгБЛпЉЯгААдї•дЄЛгБЂињ∞гБєгВЛ3гБ§гБЃгГЖгВѓгГОгГ≠гВЄгГЉгБМгАБзПЊеЬ®еЕ®еЫљгБЃжВ£иАЕйБФгБЂжПРдЊЫгБХгВМгБ¶гБКгВКгАБгБЭгБЃеБ•еЇЈзЃ°зРЖгВТеЃєжШУгБЂгБЧгБ¶гБДгВЛгАВ
вЧПжВ£иАЕеРСгБСгВµгВ§гГИпЉИPatient portalsпЉЙ
жВ£иАЕйБФгБМеМїиАЕгБЃгВ™гГХгВ£гВєгБЂйЫїи©±гВТгБЩгВЛгБЃгБѓгБ©гВУгБ™зРЖзФ±гБЛгВЙгБ†гВНгБЖгБЛпЉЯгААдЄїгБ™зРЖзФ±гБѓгАБж§ЬжЯїзµРжЮЬгВТзЯ•гВЛгБЯгВБгАБеЗ¶жЦєзЃЛгБЃи£ЬеЕЕгВТдЊЭй†ЉгБЩгВЛгБЯгВБгАБгВҐгГЭгВ§гГ≥гГИгГ°гГ≥гГИгВТеПЦгВЛгБЯгВБгБ†гАВгБЭгВМгВЙгБЃгГЧгГ≠гВїгВєгВТз∞°жШУеМЦгБЩгВЛгБЂгБѓжФѓжЙХгБДжЦєж≥ХгАБе∞ВйЦАеИЖйЗОгАБгВ™гГХгВ£гВєгБЃе†іжЙАгВТгВВгБ®гБЂеМїиАЕгВТжОҐгБЩгБУгБ®гБЃгБІгБНгВЛжВ£иАЕеРСгБСгВµгВ§гГИгВТе∞ОеЕ•гБЩгВЛгБУгБ®гБ†гАВжВ£иАЕгБМиЗ™еИЖгБЃгВ≥гГ≥гГФгГ•гГЉгВњгБЛжРЇеЄѓйЫїи©±гБЛгВЙгГ≠гВ∞гВ™гГ≥гБЧгАБж§ЬжЯїзµРжЮЬгВТзЯ•гВКгАБи≥™еХПгБЧгАБгГ™гВѓгВ®гВєгГИгВТйАБдњ°гБІгБНгВМгБ∞гАБеЃЪжЬЯеБ•и®ЇгВТйБњгБСгБЯгВКгАБеМїиАЕгБЂдЉЪгБЖгБЃгВТеїґжЬЯгБЩгВЛеП£еЃЯгБѓзД°гБПгБ™гВЛгБѓгБЩгБ†гАВ
вЧПгГҐгГРгВ§гГЂгВҐгГЧгГ™пЉИMobile appsпЉЙ
жРЇеЄѓжАІгБѓгВВгБѓгВДзЙєжЃКгБ™гВВгБЃгБІгБѓгБ™гБПгАБељУзДґгБЃгВВгБЃгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгВЛгАВeMarketerз§ЊгБѓ2014еєіжЬЂгБЊгБІгБЂ17еДД6еНГдЄЗдЇЇгБЃдЇЇгАЕгБМгВєгГЮгГЉгГИгГХгВ©гГ≥гВТжМБгБ°гАБдљњзФ®гБЩгВЛгВИгБЖгБЂгБ™гВЛгБ†гВНгБЖгАБгБ®гБДгБЖз†Фз©ґзЩЇи°®гВТгБЧгБЯгАВгБУгБЃжХ∞е≠ЧгБѓдЄЦзХМдЇЇеП£гБЃ1/4гБЂзЫЄељУгБЩгВЛгАВдЇЇгАЕгБѓењЕи¶БгБ™гБУгБ®гБЩгБєгБ¶гБЂиЗ™еИЖгБЃйЫїи©±гБЛгВЙгВҐгВѓгВїгВєгБЧгБЯгБДгБЃгБ†гАВгБЭгВМгБѓеБ•еЇЈи®ЇжЦ≠гБЃи®ШйМ≤гАБи®ЇеѓЯж≠ігАБгГРгВ§гВњгГЂгВµгВ§гГ≥гБЃжХ∞еА§гБЃгБњгБ™гВЙгБЪгАБгВҐгГЭгВТеПЦгВЛгБ®гБДгБ£гБЯи°МзВЇгВВеРЂгВАгАВгБ°гВЗгБЖгБ©еРДеАЛдЇЇгБМгГҐгГРгВ§гГЂгВҐгГЧгГ™гВТдљњгБ£гБ¶иЗ™еИЖгБЃйКАи°МжГЕ冱гБЂгВҐгВѓгВїгВєгБІгБНгВЛгБЃгБ®еРМгБШгВИгБЖгБЂгАБиЗ™еИЖгБЃеМїзЩВи®ШйМ≤гВТеН≥еЇІгБЂеЕ•жЙЛгБІгБНгВЛењЕи¶БгБМгБВгВЛгАВ1йА±йЦУеЊМгБЂгБЭгВМгВЙгБЃеН∞еИЈзЙ©гБМйГµдЊњгБІгВДгБ£гБ®е±КгБПгВИгБЖгБІгБѓгБ†гВБгБ™гБЃгБ†гАВеРДз®ЃгГЗгГРгВ§гВєгВТйІЖдљњгБЩгВЛгБУгБ®гБІгАБжЧ•еЄЄжіїеЛХгАБзЭ°зЬ†гАБи°АеЬІгАБдљУйЗНгВТињљиЈ°зЃ°зРЖгБЩгВЛгБЃгБМеЃєжШУгБЂгБ™гВЛгАВ
вЧПйБ†йЪФеМїзЩВпЉИTelehealthпЉЙ
гБ©гБ°гВЙгБЂгБЧгБ¶гВВжВ£иАЕгБЯгБ°гБМи®ЇзЩВжЙАгБЂи°МгБПгБЃгВТж≠ҐгВБгВЛгБУгБ®гБѓгБІгБНгБЭгБЖгБЂгБ™гБДгБ®жАЭгВПгВМгВЛдЄАжЦєгБІгАБйБ†йЪФеМїзЩВгБЂгВИгБ£гБ¶йБ†йЪФгБЛгВЙж≤їзЩВгБЩгВЛгБУгБ®гБМеПѓиГљгБЂгБ™гВКгБ§гБ§гБВгВЛгАВгБЭгБЃеИ©зВєгБѓи®АгБЖгБЊгБІгВВгБ™гБДгБМгАБгБХгВЙгБЂйЗНи¶БгБ™зВєгБѓгАБеМїеЄЂгБ®жВ£иАЕйЦУгБЃгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥гВТгВИгВКиЙѓгБПгБЩгВЛгБУгБ®гБЂгБ§гБ™гБМгВЛгБУгБ®гБ†гАВдЄАдЊЛгВТжМЩгБТгВИгБЖгАВз≥Це∞њзЧЕжВ£иАЕгБМEHRпЉИйЫїе≠РеБ•еЇЈи®ШйМ≤пЉЙгБЂгГ™гГ≥гВѓгБЧгБЯгГҐгГРгВ§гГЂгВҐгГЧгГ™гВТдљњзФ®гБЩгВЛгБ®гАБжЧ•гАЕгБЃи°Аз≥ЦеА§гБМи®ШйМ≤гБХгВМгАБгГҐгГРгВ§гГЂгВҐгГЧгГ™гБЂгВҐгГГгГЧгГ≠гГЉгГЙгБХгВМгАБдњЭе≠ШгБХгВМгВЛгАВжХ∞еА§гБЂеҐЧеК†гБМи¶ЛгВЙгВМгВЛгБ®гАБеМїеЄЂгБЂи≠¶еСКгБМе±КгБНгАБгБХгВЙгБ™гВЛгГ™гВєгВѓгБѓеЫЮйБњгБІгБНгВЛгАБгБ®гБДгБЖгВПгБСгБ†гАВжВ£иАЕйБФгБѓиЗ™еИЖгБЃеБ•еЇЈгБЂгВИгВКйЦҐењГгВТеРСгБСгАБжѓОжЧ•и®ШйМ≤гВТгБ§гБСгВЛгБУгБ®гБЂгВИгБ£гБ¶гАБиЗ™еИЖгБЃзФЯжіїзњТжЕ£гБЂгВИгВКж∞ЧгВТйЕНгВЛгБУгБ®гБЂгБ§гБ™гБМгВЛеПѓиГљжАІгВВгБВгВЛгАВ
гГШгГЂгВєгВ±гВҐгБЂгБКгБСгВЛжКАи°УйЭ©жЦ∞гБЃжБ©жБµгБѓи®ИгВКзЯ•гВМгБ™гБДгВВгБЃгБМгБВгВКгАБ2014еєігБЃеЛХеРСгБѓж∞Је±±гБЃдЄАиІТгБЂгБЩгБОгБ™гБДгАВжРЇеЄѓйЫїи©±гБЃдљњзФ®гБМжА•еҐЧгБЧгАБгГЗгВЄгВњгГЂеМЦгБХгВМгБЯеБ•еЇЈзЃ°зРЖжЦєж≥ХгБМжА•йАЯгБЂеПЦгВКеЕ•гВМгВЙгВМгВЛгВИгБЖгБЂгБ™гБ£гБ¶гАБеМїеЄЂгБЯгБ°гБѓиЗ™еИЖгБЃеМїзЩВи°МзВЇгВДжВ£иАЕгБЂгБ®гБ£гБ¶гБ©гВМгБМжЬАйБ©гБ™жКАи°УгБЛгВТиАГгБИгВЛењЕи¶БгБМгБВгВЛгБ®и®АгБИгВЛгАВгБ§гБЊгВКгГЖгВѓгГОгГ≠гВЄгГЉгБУгБЭгАБжВ£иАЕйБФгБЃгБХгВЙгБ™гВЛеБ•еЇЈгБЄгБЃйНµгБ™гБЃгБ†гАВ
и®ШдЇЛеОЯжЦЗгБѓгБУгБ°гВЙпЉИгАОmHealth NewsгАП8жЬИ18жЧ•жО≤иЉЙпЉЙ
вАїи®ШдЇЛеЕђйЦЛгБЛгВЙжЧ•жХ∞гБМзµМйБОгБЧгБЯеОЯжЦЗгБЄгБЃгГ™гГ≥гВѓгБѓгАБж≠£еЄЄгБЂйБЈзІїгБЧгБ™гБДе†іеРИгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВгБФдЇЖжЙњгБПгБ†гБХгБДгАВ
пЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭпЉЭ
гАОmHealth WatchгАПгБЃи¶ЦзВєпЉБ
дїКеЫЮж≥®зЫЃгБЃгГЛгГ•гГЉгВєгБѓгАБжВ£иАЕгБЂеКЫгВТдЄОгБИгВЛ3гБ§гБЃmHealthжКАи°УгБЂйЦҐгБЩгВЛи®ШдЇЛгБІгБЩгАВ
жИСгАЕгБМгАБMobile HealthгБЃеИЖйЗОгВТи¶ЛзґЪгБСгБ¶гБДгВЛгБ™гБЛгБІгАБжЧ•з±≥йЦУгБЃйБХгБДгВТйЭЮеЄЄгБЂеЉЈгБПжДЯгБШгВЛгБЃгБМгАБеМїеЄЂгБ®жВ£иАЕгБ®гБЃи®ЇеѓЯдї•е§ЦгБЂгАМMobileгАНгВТжіїзФ®гБЧгБЯгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥жіїеЛХгБМжіїзЩЇгБ™з±≥еЫљгБЂжѓФгБєгАБжЧ•жЬђгБІгБѓи®ЇеѓЯжЩВдї•е§ЦгБІгБЃгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥йГ®еИЖгБЂгБЊгБ£гБЯгБПгВҐгГЧгГ≠гГЉгГБгБХгВМгБ¶гБДгБ™гБДгБУгБ®гБІгБЩгАВ
дїКеЫЮгБЃгГЛгГ•гГЉгВєгБІгБѓгАБжВ£иАЕгБЂжПРдЊЫгБХгВМгБ¶гБДгВЛеБ•еЇЈзЃ°зРЖгВТеЃєжШУгБЂгБЩгВЛгГЖгВѓгГОгГ≠гВЄгГЉгБ®гБЧгБ¶гАБдї•дЄЛ3гБ§гВТзієдїЛгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
1.гАМжВ£иАЕеРСгБСгВµгВ§гГИпЉИPatient portalsпЉЙгАН
2.гАМгГҐгГРгВ§гГЂгВҐгГЧгГ™пЉИMobile appsпЉЙгАН
3.гАМйБ†йЪФеМїзЩВпЉИTelehealthпЉЙгАН
дЄКи®Ш3гБ§гБЃжКАи°УгГїгВµгГЉгГУгВєгВТи¶ЛгВЛгБ®гАБжВ£иАЕгБЃеБ•еЇЈзЃ°зРЖгВТз∞°жШУгБЂгБЩгВЛгБУгБ®гБМзЫЃзЪДгБІгБѓгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБеМїеЄЂгВДе∞ВйЦАеЃґгБ®гБЃгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥гВТеЃєжШУгБЂгБЩгВЛгБУгБ®гВВжВ£иАЕгБЃеБ•еЇЈзЃ°зРЖгБЃдЄАйГ®гБ®гБЧгБ¶жНЙгБИгБ¶гБДгВЛгАБгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВ
жЧ•жЬђгБІгБЃгГҐгГРгВ§гГЂгВҐгГЧгГ™гБЃзКґж≥БгВТи¶ЛжЄ°гБЧгБ¶гБњгВЛгБ®гАБеМїеЄЂгВДгБЭгБЃдїЦгБЃеБ•еЇЈйЦҐйА£гБЃе∞ВйЦАеЃґгБ®гБЃгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥гВТдњГйА≤гБХгБЫгВЛж©ЯиГљгВТзЫЫгВКиЊЉгВУгБ†гВҐгГЧгГ™гБѓйЭЮеЄЄгБЂе∞СгБ™гБПгАБеЯЇжЬђзЪДгБЂгБѓеИ©зФ®иАЕгБМиЗ™иЇЂгБЃгГЗгГЉгВњгВДжГЕ冱гВТзЃ°зРЖгБЩгВЛгВҐгГЧгГ™гБМдЄАиИђзЪДгБІгБЩгАВ
гГҐгГРгВ§гГЂгВҐгГЧгГ™гБЂеМїеЄЂгВДгБЭгБЃдїЦгБЃеБ•еЇЈйЦҐйА£гБЃе∞ВйЦАеЃґгБ®гБЃгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥гВТдњГйА≤гБХгБЫгВЛж©ЯиГљгВТзЫЫгВКиЊЉгВАгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБѓгАБеИґеЇ¶гВДеИґзіДгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБІйЫ£гБЧгБДйГ®еИЖгВВгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБгБЭгВМгВИгВКгВВгГПгГЉгГЙгГЂгБМйЂШгБДгБЃгБМгАБеѓЊењЬгБЩгВЛгБЯгВБгБЃгВµгГЉгГУгВєжПРдЊЫгВДеѓЊењЬи≤†иНЈгБЂгБ™гБ£гБ¶гБНгБЊгБЩгАВ
гБЧгБЛгБЧгАБгГҐгГРгВ§гГЂгВҐгГЧгГ™еНШдљУгБІгБЃгГЮгГНгВњгВ§гВЇгБМйЫ£гБЧгБПгБ™гБ£гБ¶гБНгБ¶гБДгВЛгБ™гБЛгБІгАБеМїеЄЂгВДе∞ВйЦАеЃґгБ®гБЃгВ≥гГЯгГ•гГЛгВ±гГЉгВЈгГІгГ≥ж©ЯиГљгАБдЇЇгБМдїЛеЬ®гБЩгВЛгВµгГЉгГУгВєгВТзЫЫгВКиЊЉгВАгБУгБ®гБѓгАБйАЖгБЂгГЮгГНгВњгВ§гВЇгБ®гБДгБЖи¶≥зВєгБЛгВЙгВВењЕи¶БгБ™ж©ЯиГљгБ®и®АгБИгБЊгБЩгАВ
гБ™гБЬгБ™гВЙгАБдЇЇгВДгГҐгГОгВДе†іжЙАгБ®гБДгБ£гБЯгГ™гВҐгГЂгБМзµ°гВАгБ®гБУгВНгБЂгБѓгБКйЗСгВТжФѓжЙХгБЖгАМжЦЗеМЦгАНгБМгАБгБЩгБІгБЂе≠ШеЬ®гБЧгБ¶гБДгВЛгБЛгВЙгБІгБЩгАВ
гБКйЗСгВТжФѓжЙХгБЖжЦЗеМЦгБМгБЊгБ†гБЊгБ†жИРзЂЛгБЧгБ¶гБДгБ™гБДгГҐгГРгВ§гГЂгВҐгГЧгГ™гБЛгВЙгАБе¶ВдљХгБЂгБКйЗСгВТжФѓжЙХгБЖгАМжЦЗеМЦгАНгБМе≠ШеЬ®гБЩгВЛй†ШеЯЯгБЂи™Ше∞ОгБЩгВЛгБЃгБЛгБМгАБдїКеЊМгБЃгГҐгГРгВ§гГЂгВҐгГЧгГ™гВТеРЂгВБгБЯmHealthй†ШеЯЯгБЂжђ†гБЛгБЫгБ™гБДи¶ЦзВєгБЂгБ™гБ£гБ¶гБПгВЛгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ
и®АгБДгБЛгБИгВМгБ∞гАБеИ©зФ®иАЕгБ®е∞ВйЦАеЃґгВТгГЗгГЉгВњгВДжГЕ冱гВТеРЂгВБгБ¶зЫіжО•гБ§гБ™гБРгБУгБ®гБУгБЭгАБгАМmHealthгАНгБЃжКАи°УгБЃйА≤еМЦгБІж±ВгВБгВЙгВМгБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБ™гБЃгБЛгВВгБЧгВМгБЊгБЫгВУгАВ
 гАОmHeath WatchгАПзЈ®йЫЖеІФеУ°гААйЗМи¶ЛгААе∞ЖеП≤
гАОmHeath WatchгАПзЈ®йЫЖеІФеУ°гААйЗМи¶ЛгААе∞ЖеП≤
憙еЉПдЉЪз§ЊгВєгГЭгГЂгГДгБЃгГЗгВ£гГђгВѓгВњгГЉгБ®гБЧгБ¶гАБдЄїгБЂеБ•еЇЈз≥їгВ¶гВІгГЦгВµгВ§гГИгАБгВ≥гГ≥гГЖгГ≥гГДгБ™гБ©гБЃдЉБзФїгГїеИґдљЬгГїйБЛеЦґгВТжЛЕељУгАВгБЊгБЯгАОHealth Biz Watch AcademyгАПгБІгБѓгАБгАМmHealthгАНгБЃгВїгГЯгГКгГЉиђЫеЄЂгБ®гБЧгБ¶иІ£и™ђгАВпЉИдЄАи≤°пЉЙзФЯжґѓе≠¶зњТйЦЛзЩЇи≤°еЫ£и™НеЃЪгВ≥гГЉгГБгАВ
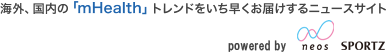



Comments are closed.