م€ژmHealth Watchم€ڈمپ§مپ¯م€پمپ“مپ“وœ€è؟‘مپ§ه…¬é–‹مپ•م‚Œمپںمƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ‹م‚‰م€Œو³¨ç›®مƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹م€چم‚’مƒ”مƒƒم‚¯م‚¢مƒƒمƒ—مپ—م€پ独è‡ھمپ®è¦–点مپ§è§£èھ¬مپ—مپ¦مپ„مپچمپ¾مپ™م€‚
ن»ٹه›و³¨ç›®مپ—مپںمƒ‹مƒ¥مƒ¼م‚¹مپ¯مپ“مپ،م‚‰ï¼پ
ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼
“èھ؟وں»: و¶ˆè²»è€…مپ®80%مپŒمƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹م‚’هˆ©ç”¨مپ—مپںمپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚‹â€

Rock Healthمپ®م€Œ2022ه¹´ç‰ˆمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒکمƒ«م‚¹و¶ˆè²»è€…و™®هڈٹèھ؟وں»ï¼ˆDigital Health Consumer Adoption Survey)م€چمپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€په…¨ه›ç”者مپ®80ï¼…مپŒمپ“م‚Œمپ¾مپ§مپ«مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹ï¼ˆéپ éڑ”هŒ»ç™‚)م‚’هˆ©ç”¨مپ—مپںمپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚ٹم€پçڈ¾هœ¨مپ¯ه‡¦و–¹ç®‹مپ®هڈ—مپ‘هڈ–م‚ٹم‚„軽症مپ®و²»ç™‚مپ®مپںم‚پمپ®وœ›مپ¾مپ—مپ„و‰‹و®µمپ¨مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹مپ“مپ¨مپŒم‚ڈمپ‹مپ£مپںم€‚
مپ“مپ®èھ؟وں»مپ¯م€پç±³ه›½مپ®وˆگن؛؛8,014ن؛؛مپ«مƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒکمƒ«م‚¹مپ«é–¢مپ™م‚‹çµŒé¨“مپ«مپ¤مپ„مپ¦ه°‹مپمپںم‚‚مپ®مپ م€‚éپژهژ»1ه¹´ن»¥ه†…مپ§مپ¯م€پéں³ه£°مپ®مپ؟مپٹم‚ˆمپ³éهگŒوœںمپ®مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹مپŒوœ€م‚‚ه¤ڑمپڈهˆ©ç”¨مپ•م‚Œمپںمپ“مپ¨مپŒوکژم‚‰مپ‹مپ«مپھمپ£مپ¦مپ„م‚‹م€‚
م‚¦م‚§م‚¢مƒ©مƒ–مƒ«مƒ‡مƒگم‚¤م‚¹مپ®و™®هڈٹçژ‡م‚‚ن¸ٹوک‡مپ—مپںمپŒم€پمپ“مپ†مپ—مپںمƒ‡مƒگم‚¤م‚¹مپ®è‡¨ه؛ٹهˆ©ç”¨مپ¯م€پو¶ˆè²»è€…مپ«ç›´وژ¥وڈگن¾›مپ•م‚Œم‚‹ï¼ˆD2C)مپ¾مپ§مپ®و°´و؛–مپ«مپ¯è‡³مپ£مپ¦مپ„مپھمپ„م€‚مپ¾مپںم€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒکمƒ«م‚¹م‚¢مƒ—مƒھم‚„م‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆم€پمƒکمƒ«م‚¹مƒ†م‚¯مƒژمƒم‚¸مƒ¼ن¼پو¥مپ¨مپ®مƒ‡مƒ¼م‚؟ه…±وœ‰مپ«ه¯¾مپ™م‚‹و¶ˆè²»è€…مپ®و„ڈو¬²مپ¯م€پهŒ»ه¸«م‚„臨ه؛ٹهŒ»مپ«ه¯¾مپ™م‚‹ن؟،é ¼مپ¨و¯”較مپ™م‚‹مپ¨مپ¾مپ ن½ژمپ„م€‚
2022ه¹´مپ¯مپ“م‚Œمپ¾مپ§هچپهˆ†مپھهŒ»ç™‚م‚µمƒ¼مƒ“م‚¹م‚’هڈ—مپ‘م‚‰م‚Œمپھمپ‹مپ£مپںم‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ«مپٹمپ‘م‚‹مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹مپ®هˆ©ç”¨çژ‡مپŒé«کمپ¾مپ£مپںم€‚مƒ’م‚¹مƒ‘مƒ‹مƒƒم‚¯ç³»و¶ˆè²»è€…مپ®مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹هˆ©ç”¨çژ‡مپ¯82%مپ«éپ”مپ—مپ¦مپٹم‚ٹم€پ2021ه¹´مپ‹م‚‰9مƒم‚¤مƒ³مƒˆن¸ٹوک‡مپ—م€پèھ؟وں»ه¯¾è±،مپ¨مپھمپ£مپںمپ™مپ¹مپ¦مپ®ن؛؛種مƒ»و°‘و—ڈم‚°مƒ«مƒ¼مƒ—مپ®ن¸مپ§وœ€م‚‚é،•è‘—مپھن¼¸مپ³م‚’ç¤؛مپ—مپںم€‚
ه‰چه¹´و¯”مپ§وœ€م‚‚ه¢—هٹ مپ—مپںمپ®مپ¯م€پ2021ه¹´مپ®64%مپ‹م‚‰76%مپ«ه¢—هٹ مپ—مپں55و³ن»¥ن¸ٹمپ®ه›ç”者م€پ60%مپ‹م‚‰73%مپ«ه¢—هٹ مپ—مپںهœ°و–¹هœ¨ن½ڈ者م€پ37%مپ‹م‚‰50%مپ«ه¢—هٹ مپ—مپںهپ¥ه؛·ن؟é™؛وœھهٹ ه…¥è€…مپ م€‚
مƒ“مƒ‡م‚ھمƒ»مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹مپ®هˆ©ç”¨çژ‡مپ¯2021ه¹´مپ‹م‚‰م‚„م‚„و¨ھمپ°مپ„مپ مپ£مپںمپŒم€پن»–مپ®مپ™مپ¹مپ¦مپ®مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹و‰‹و®µمپ«مپٹمپ„مپ¦هˆ©ç”¨çژ‡مپ®ه¢—هٹ مپŒè¦‹م‚‰م‚Œمپںم€‚éں³ه£°é€ڑ話مپ¯12مƒم‚¤مƒ³مƒˆه¢—مپ®57%م€پهپ¥ه؛·م‚¢مƒ—مƒھم‚„م‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆçµŒç”±مپ®مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹مپ¯11مƒم‚¤مƒ³مƒˆه¢—مپ®48%م€پمƒ،مƒ¼مƒ«مƒ»مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹مپ¯9مƒم‚¤مƒ³مƒˆه¢—مپ®43%م€پمƒ†م‚م‚¹مƒˆمƒ،مƒƒم‚»مƒ¼م‚¸مپ¯8مƒم‚¤مƒ³مƒˆه¢—مپ®36%مپ¨مپھمپ£مپںم€‚
وœ¬èھ؟وں»مپ®هں·ç†è€…م‚‰مپ¯م€پم‚¦م‚§م‚¢مƒ©مƒ–مƒ«ç«¯وœ«مپ®ن½؟用çژ‡مپ¯و¨ھمپ°مپ„مپ§مپ‚مپ£مپںمپŒم€پé«ک齢者م€پن½ژو‰€ه¾—者م€پن½ژه¦و´è€…مپ®م‚¦م‚§م‚¢مƒ©مƒ–مƒ«ç«¯وœ«و‰€وœ‰çژ‡مپ¯2021ه¹´مپ®18%مپ‹م‚‰ن¸ٹوک‡مپ—م€پ21%مپ¨éپژهژ»وœ€é«کمپ¨مپھمپ£مپںمپ“مپ¨م‚’وŒ‡و‘کمپ—مپ¦مپ„م‚‹م€‚
مپ—مپ‹مپ—م€پهپ¥ه؛·çٹ¶و…‹مپŒو‚ھمپ„مپ¨ç”مپˆمپںه›ç”者م‚ˆم‚ٹم‚‚هپ¥ه؛·مپھه›ç”者مپ®و–¹مپŒم‚¦م‚§م‚¢مƒ©مƒ–مƒ«ç«¯وœ«م‚’و‰€وœ‰مپ™م‚‹ه‚¾هگ‘مپŒمپ‚م‚ٹم€پم€Œç–¾ç—…ç®،çگ†م‚’و”¹ه–„مپ—مپںم‚ٹم€پ疾病مپ®é€²è،Œم‚’監視مپ™م‚‹م‚¦م‚§م‚¢مƒ©مƒ–مƒ«ç«¯وœ«م‚’ه€‹ن؛؛مپ«è،Œمپچه±ٹمپ‹مپ›مپںم‚ٹمپ™م‚‹مپںم‚پمپ«مپ¯م€پمپ•م‚‰مپ«ه¤ڑمپڈم‚’è،Œمپ†ï¼ˆه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚‹ï¼‰م€چمپ¨مپ—مپںم€‚
هپ¥ه؛·وƒ…ه ±مپ®ه…¥و‰‹ه…ˆمپ«مپ¤مپ„مپ¦مپ¯م€پمƒ‡م‚¸م‚؟مƒ«مƒکمƒ«م‚¹م‚¢مƒ—مƒھ(28%)م€پم‚¦م‚§مƒ–م‚µم‚¤مƒˆï¼ˆ16%)م€پمƒکمƒ«م‚¹مƒ†م‚¯مƒژمƒم‚¸مƒ¼ن¼پو¥ï¼ˆ15%)م€پم‚½مƒ¼م‚·مƒ£مƒ«مƒ،مƒ‡م‚£م‚¢م‚°مƒ«مƒ¼مƒ—(11%)مپ¨و¯”較مپ—مپ¦م€پ77ï¼…مپ®ه›ç”者مپŒهŒ»ه¸«م‚„臨ه؛ٹهŒ»م‚’ن؟،é ¼مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ¨ه›ç”مپ—مپںم€‚
è¨کن؛‹هژںو–‡مپ¯مپ“مپ،م‚‰ï¼ˆم€ژmobihealthnewsم€ڈ2023ه¹´2وœˆ28و—¥وژ²è¼‰ï¼‰
※è¨کن؛‹ه…¬é–‹مپ‹م‚‰و—¥و•°مپŒçµŒéپژمپ—مپںهژںو–‡مپ¸مپ®مƒھمƒ³م‚¯مپ¯م€پو£ه¸¸مپ«éپ·ç§»مپ—مپھمپ„ه ´هگˆمپŒمپ‚م‚ٹمپ¾مپ™م€‚مپ”ن؛†و‰؟مپڈمپ مپ•مپ„م€‚
ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼ï¼
م€ژmHealth Watchم€ڈمپ®è¦–点ï¼پ
ن»¥ه‰چç´¹ن»‹مپ—مپںمƒکمƒ«م‚¹م‚±م‚¢مƒ†م‚¯مƒژمƒم‚¸مƒ¼م‚؛مپ®èھ؟وں»مپ«م‚ˆم‚‹مپ¨م€پم€Œه›½ه†…مپ®م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療مپ®èھچçں¥مپ¯88.9%م‚‚مپ‚م‚‹مپŒم€پم‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³è¨؛療م‚’ه®ںéڑ›مپ«ن½؟مپ£مپںمپ“مپ¨مپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ¯8%مپ«ç•™مپ¾م‚‹م€چمپ¨مپ®مپ“مپ¨مپ§مپ—مپںم€‚
ن»ٹه›ç´¹ن»‹مپ—مپںç±³ه›½مپ®مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹مپ®ه®ںو…‹مƒ¬مƒمƒ¼مƒˆمپ¯مپ„مپ‹مپŒمپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ںو—¥وœ¬مپ§è€ƒمپˆم‚‹مپ¨مپ¨مپ¦مپ¤م‚‚مپھمپڈé«کمپ„و•°ه—مپ مپ¨و€مپ„مپ¾مپ›م‚“مپ‹ï¼ں
ç±³ه›½مپ¯و—¥وœ¬مپ¨éپ•مپ„م€پو–°ه‹م‚³مƒمƒٹمپ«م‚ˆم‚ٹن¸€و™‚مƒمƒƒم‚¯مƒ€م‚¦مƒ³م‚’مپ—مپ¦مپ„مپ¾مپ—مپںمپ®مپ§م€په¼·هˆ¶çڑ„مپ«مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹م‚’ن½“験مپ™م‚‹مپ“مپ¨مپŒمپ§مپچمپ¾مپ—مپںم€‚
و—¥وœ¬مپ®ه ´هگˆمپ¯مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹مپŒن½؟مپˆم‚‹م‚ˆمپ†مپ«مپ¯مپھم‚ٹمپ¾مپ—مپںمپŒم€پ(هˆ¶é™گمپ¯مپ‚م‚Œمپ©ï¼‰é€ڑ院م‚‚هڈ¯èƒ½مپ§مپ¯مپ‚م‚ٹمپ¾مپ—مپںمپ®مپ§م€په¼·هˆ¶çڑ„مپ«ن½؟مپ†مپ¾مپ§مپ¯مپ„مپ‹مپڑم€پèھچçں¥مپ¯مپ•م‚Œمپ¦م‚‚هˆ©ç”¨مپ«مپ¯مپ¤مپھمپŒم‚ٹمپ¾مپ›م‚“مپ§مپ—مپںم€‚
مپںمپ م€پéپژç–ژهœ°م‚’ن¸ه؟ƒمپ«هŒ»ç™‚ن¸چ足مپ¯و·±هˆ»مپ§مپ™مپ®مپ§م€پن»ٹه¾Œم‚‚مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹مپŒو—¥وœ¬مپ§مپ¯ه؛ƒمپŒم‚‰مپھمپ„مپ¨مپ„مپ†مپ“مپ¨مپ¯مپھمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
ن»ٹه¾Œمپ®مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹و™®هڈٹمپ®مپںم‚پمپ«هڈ‚考مپ«مپ—مپںمپ„مپ®مپŒه…ˆè،Œمپ™م‚‹ç±³ه›½مپ®ه‹•هگ‘مپ§مپ™م€‚
مƒ“مƒ‡م‚ھمƒ»مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹ï¼ˆé،”مپŒè¦‹مپˆم‚‹مƒ†مƒ¬مƒ“電話مپ®çٹ¶و…‹ï¼‰مپ®هˆ©ç”¨çژ‡مپ¯و¨ھمپ°مپ„مپھمپ®مپ«ه¯¾مپ—م€پéں³ه£°م€پمƒ،مƒ¼مƒ«م€پم‚¢مƒ—مƒھمپ§مپ®م‚³مƒںمƒ¥مƒ‹م‚±مƒ¼م‚·مƒ§مƒ³مپھمپ©مپ®هˆ©ç”¨çژ‡مپŒن¸ٹمپŒمپ£مپ¦مپ„مپ¾مپ™م€‚
مپ“م‚Œمپ¯م‚¹مƒمƒ¼مƒˆمƒ•م‚©مƒ³مپ®و™®و®µن½؟مپ„مپŒه½±éں؟مپ—مپ¦مپ„م‚‹مپ¨è€ƒمپˆم‚‰م‚Œمپ¾مپ™م€‚م‚ھمƒ³مƒ©م‚¤مƒ³ن¼ڑè°مپ§م‚‚مپھمپ„é™گم‚ٹم€پé »ç¹پمپ«é،”م‚’見مپھمپŒم‚‰ن¼ڑ話مپ™م‚‹م‚ˆمپ†مپھن½؟مپ„و–¹م‚’مپ™م‚‹ن؛؛مپŒمپ©م‚Œمپ مپ‘مپ„م‚‹مپ§مپ—م‚‡مپ†مپ‹ï¼ںم‚ˆم‚ٹو‰‹è»½مپھéں³ه£°مپ®مپ؟م€پو–‡ه—وƒ…ه ±مپ®مپ؟مپ®و–¹مپŒوٹµوٹ—مپŒمپھمپ„ن؛؛م‚‚ه¤ڑمپڈمپ„مپ¾مپ™م€‚
م‚‚مپ،م‚چم‚“م€پè¨؛و–مپ«مپٹمپ„مپ¦مپ¯ç—‡çٹ¶م‚’ç›®مپ§ç¢؛èھچمپ™م‚‹مپھمپ©ه؟…è¦پمپھه ´é¢مپ¯ه¤ڑم€…مپ‚م‚ٹمپ¾مپ™مپ®مپ§م€پن½؟مپ„ه‹و‰‹مپ®مپںم‚پمپ مپ‘مپ«ه‹•ç”»و©ں能مپ¯مپ„م‚‰مپھمپ„مپ¨مپ¯مپھم‚‰مپھمپ„مپ§مپ—م‚‡مپ†م€‚
و—¥وœ¬مپ«مپٹمپ‘م‚‹ن»ٹه¾Œمپ®مƒ†مƒ¬مƒکمƒ«م‚¹و™®هڈٹمپ®مپںم‚پمپ«مپ¯م€پو©ں能çڑ„مپھ点مپ مپ‘مپ§è€ƒمپˆم‚‹مپ®مپ§مپ¯مپھمپڈم€پمپ‚م‚‰م‚†م‚‹é¢مپ§وٹµوٹ—و„ںم‚’مپھمپڈمپ—مپ¦مپ„مپڈم‚¹مƒ†مƒƒمƒ—م‚’ن½œمپ£مپ¦مپ„مپڈه؟…è¦پمپŒمپ‚م‚‹مپ®مپ§مپ¯مپھمپ„مپ‹مپ¨و€مپˆمپ¾مپ™م€‚
 م€ژmHeath Watchم€ڈ編集م€€و¸،è¾؛م€€و¦هڈ‹
م€ژmHeath Watchم€ڈ編集م€€و¸،è¾؛م€€و¦هڈ‹
و ھه¼ڈن¼ڑ社م‚¹مƒمƒ«مƒ„مپ«مپ¦هپ¥ه؛·مƒ“م‚¸مƒچم‚¹مپ«مپٹمپ‘م‚‹مƒمƒ¼م‚±مƒ†م‚£مƒ³م‚°مپ«é–¢مپ™م‚‹م‚³مƒ³م‚µمƒ«مƒ†م‚£مƒ³م‚°م€پن¸€èˆ¬ç¤¾ه›£و³•ن؛؛ 社ن¼ڑçڑ„هپ¥ه؛·وˆ¦ç•¥ç ”究و‰€مپ®çگ†ن؛‹مپ¨مپ—مپ¦م€پم‚¦م‚§مƒ«مƒ“مƒ¼م‚¤مƒ³م‚°مپ®ç¤¾ن¼ڑه®ں装و–¹و³•مپ®ç ”究م‚’è،Œمپ†م€‚مپ¾مپںم‚¦م‚§م‚¢مƒ©مƒ–مƒ«و©ںه™¨م€پهپ¥ه؛·مƒ“م‚¸مƒچم‚¹مƒ¢مƒ‡مƒ«مپ«é–¢مپ™م‚‹هپ¥ه؛·مƒ،مƒ‡م‚£م‚¢مپ§مپ®ç™؛è،¨م‚„م€پمƒکمƒ«م‚¹م‚±م‚¢ITمپھمپ©مپ§è¬›و¼”م‚’è،Œمپ†م€‚
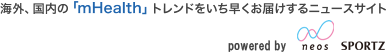



Comments are closed.